医療法人の「社団」と「財団」とは
医療法人とは、病院、診療所、介護老人保健施設などを法人として運営するために設立される、医療法に基づく法人です。
設立には都道府県への許可が必要であり、その際には、「社団」または「財団」のいずれかの形態を選択することになります。(医療法第39条第1項)
「社団」と「財団」は、いずれも非営利法人であり、剰余金の配当ができない点は共通しています。
また、一般の医療法人に加えて、社会医療法人や特定医療法人といった公益性の高い類型に移行することも可能であり、医療機関としての基本的な機能や役割に違いはありません。
では、両者の違いはどこにあるのでしょうか。
それは、法人としての設計、すなわち内部構造や運営の仕組みにあります。
体外的な区別より、内部的な組織運営の違いが本質です。
ここではまず、医療法人の社団と財団が、それぞれどのような形で設計されている組織なのか、それにより、どのような運営ができる組織なのかを見ていきましょう。
医療法人社団とは
医療法人社団は、「人」が経営の中心にある組織です。
設立にあたっては、まず「社員」と呼ばれる複数の人(※ここでの「社員」は従業員とは異なります)が集まり、資金や不動産など、医療法人の運営に必要な財産を出資し、社員を構成員とする「社員総会」で選任された役員により運営される法人となります。
必ずしも社員が財産を出資する必要はありませんが、実際には、社員が出資を行い、かつ役員である理事の地位も兼ねているケースが多く見られます。
このような医療法人社団の仕組みは、よく株式会社に例えられます。
社員は会社のオーナーである「株主」、社員総会は会社の最高意思決定機関である「株主総会」に相当します。
また、理事は取締役、理事長は代表取締役、理事会は取締役会、監事は監査役にそれぞれ置き換えて理解することができます。
一般の中小企業では、会社の株主でありながら経営も担う「オーナー社長」(株主=取締役)のケースがよく見られますが、医療法人社団も同様に、「社員=理事」であることが多く、それにより、少人数でも運営しやすい構造となっています。
たとえば、個人開業医が自身のクリニックを法人化し、自ら社員となって医療法人を設立し、その理事長に就任してクリニックの経営を継続することも、医療法人社団であれば可能です。
医療法人財団とは
医療法人財団は、「財産」を基盤とする医療法人です。
医療法人を設立するために無償で寄付された財産に法人格を与え、その財産を運用するメンバーによって法人が運営される点に特徴があります。
メンバー構成については、理事と、その業務を監査する監事を役員とする点は医療法人社団と共通していますが、それらの役員を選任するのは、「評議員」と呼ばれる人々で構成される「評議員会」です。
評議員会は理事会の決議に関与しつつ、理事および監事の選任・解任権を持ち、その職務に違反や怠慢がないかを評価することができます。
つまり、評議員会には、寄付された財産が適切に運用されるよう、役員を正しく働かせる機能があるのです。
なお、役員の選任権や解任権については、医療法人社団の社員総会も保有しています。
ただし、財団は社団と異なり、法人の中心は「財産」にあります。
寄付された「財産」が、法人の設立目的に沿う形で運用されることが活動の前提となるため、財産を運用し業務執行する立場の理事と、その選解任権をもつ評議員との兼任は、医療法人財団では認められません。
さらに、評議員の数は理事の数を上回る必要があり、その人選についても、医療従事者や有識者など、法令に基づく適任者の中から、寄附行為(社団や一般企業でいう「定款」のこと)の規定により選ばれた自然人(法人は不可)に限られます。
つまり、医療法人財団では、たとえ理事長の地位に就いたとしても、常に評議員会からの評価を受けながら職務を遂行する立場に置かれます。
仮に自身が財産を寄付して設立した法人であっても、評議員会の判断によっては経営者の地位を失うこともあり得るのです。
医療法人財団は400件未満、全体の0.7%
それでは、医療法人の総数のうち、財団の数はどのくらいあるのでしょうか。
厚生労働省の資料によると、令和6年(2024年)3月末時点での医療法人の総数は58,902であり、そのうち医療法人財団はわずか394(約0.7%)にとどまります。
この偏りは、前述のとおり、運営面でのハードルの高さに加え、医療法人財団の設立には多額の寄付を行う者の存在が前提となることが大きな要因と考えられます。
厚生労働省HP:種類別医療法人数の年次推移
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html
医療法人財団と医療法人社団の違いの一覧
医療法人財団と社団の違いを、わかりやすく一覧表で整理します。
| 社団 | 財団 | |
| 設立の基盤 | 人(社員)の集まり | 寄付された財産 |
| 運営方針 | 人(社員)の意思で運営 | 寄付された財産の目的にしたがって運営 |
| 機関設計 | 社員総会、理事会、監事 | 評議員会、理事会、監事 |
| 人員構成 | 社員総会(3名以上の社員)、理事会(3名以上の理事。うち1名が理事長)、監事(1名以上) | 評議員会(4名以上の評議員)、理事会(3名以上の理事。うち1名が理事長)、監事(1名以上) |
| 最低必要人数 | 4名以上 (社員と理事の兼任が可能であるため) | 8名以上 (評議員と理事の兼任が不可であり、かつ、理事(原則3名以上)の数を超える評議員を要するため) |
| 設立の実態 | 99%以上 | 約0.7% |
| 出資(拠出)された財産の返還 | 【持分ありの場合】 退社時などに返還請求可 【持分なしの場合】 返還請求不可(基金拠出型医療法人の場合、拠出分については要返還) | 無償の寄付であるため返還はなし |
医療法人財団のメリット
医療法人社団の場合、出資(拠出)された財産は、基本的にはそれを出資した「人」に帰属します。
特に、2007年(平成19年)以前に設立された「持分あり」の医療法人社団において、出資者は医療法人の資産に対して出資額に応じた財産権(出資持分)があり、それを定款の定めに基づき、退社時などに医療法人から払い戻してもらう権利が認められていました。
これに対して医療法人財団では、寄付された財産について払い戻すよう請求を受けるリスクはありません。
そのため、安定した財政基盤が医療法人財団の強みであるといえます。
なお、医療法人社団であっても、出資持分のない医療法人であれば、払戻しの請求を受けるリスクはありません。
しかし、厚生労働省によると、医療法人社団のうち6割以上が現在も「持分あり」の医療法人です。
また、出資持分のない医療法人の形態の一つである「基金拠出型医療法人」では、拠出された基金については返還義務があるため、この点にも留意が必要です。
こうした事情から、払い戻しや返還請求を受けるリスクがないことは、現在においても医療法人財団の大きなメリットといえるでしょう。
参考までに、令和6年(2024年)3月末時点での医療法人社団の総数58,508のうち、持分のある医療法人の数は36,393(約62%)となります。
厚生労働省HP:種類別医療法人数の年次推移
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html
医療法人財団のデメリット
医療法人社団では、開業医が自身のクリニックを法人化して理事長に就任し、家族など少人数のメンバーとともに意思決定を行いながら運営することが可能です。
また、運営規模を拡大し、より公益性の高い社会医療法人などの医療機関に発展させることも目指せます。
一方、医療法人財団の場合、運営には最低8名が必要となるため、少人数で経営したい医師にとってはハードルの高い組織となります。
さらに、前述のとおり理事と評議員の兼任が認められないため、医療法人財団は、医師個人に法人の運営権が集中しにくい構造となります。
評議員会の判断によっては、理事の地位を失うこともあり、場合によっては、自ら設立した医療法人であっても経営の実権を失うことがあるのです。
まとめ
この記事では、医療法人の2つの形態である「医療法人財団」について、「医療法人社団」との違いやメリット・デメリットを解説しました。
財団である医療法人を設立するには、法人の運営に足る寄付が必要であることに加え、実際の運営には最低8名以上の人員が求められます。
また、医師個人が自由に経営しにくい制度設計である点などが、医療法人財団が社団に比べて選ばれにくい理由といえます。

今回は、医療法人財団について、社団との違いを中心に解説しました。
社団であれば最低4名以上で運営できますし、現在、設立可能な「持分なし」の医療法人であれば、出資者からの払戻し請求のリスクもありません。
開業医の先生方が個人クリニックを法人化する際、「社団」が選ばれやすい理由がお分かりいただけたのではないでしょうか。
弊所では、医療法人の設立支援をはじめ、その後の運営まで一貫したサポートを行っております。どうぞお気軽にご相談ください。
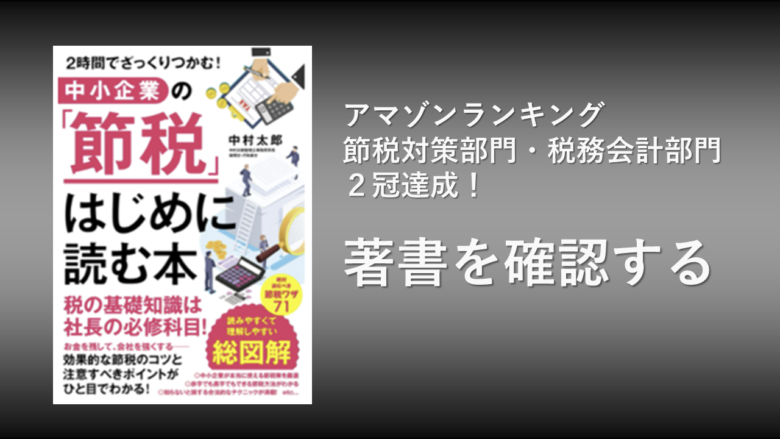



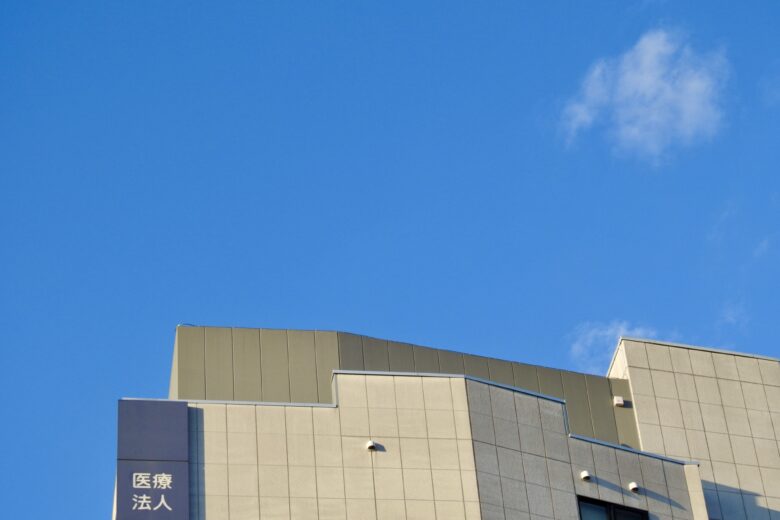














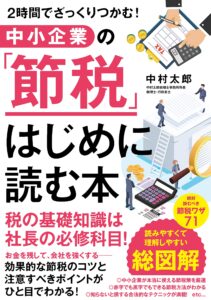

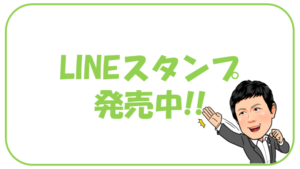
まいど!西新宿の税理士 中村です!
今回は【医療法人財団】について。
医療法人には、「社団」と「財団」という2つの形態があることをご存知でしょうか。
医療法人を設立する際は、必ずいずれかの形態を選択する必要があります。
現在、医療法人の約99%は「社団」として設立されています。
しかし、なぜここまで偏っているのか、そして「財団」には本当に魅力がないのか、そのような疑問を持たれる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、医療法人財団について、医療法人社団との違いや、医療法人財団のメリット・デメリットを解説します。