開業医が負担する税金の種類
開業医の多くは、個人事業主としてスタートします。
個人事業主になると、勤務医とは異なり、さまざまな税務を自分で行わなければなりません。
それまで知らなかった税金の存在に驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
節税対策は、まず今のご自身に、開業医としてどのような税金が課されているのかを正しく把握することから始まります。
そのため、まずは個人開業医に課される税金の種類を解説します。
55%の税負担もあり得る!所得税+住民税
開業医にとって、もっとも税負担が重くなる税は、一年間の所得に対して発生する所得税と住民税です。
特に負担が大きいのは所得税で、税率は5%~45%の超過累進税率となります。
超過累進税率とは、一定額を超える部分に対し、より高い税率が適用される仕組みのことです。
所得税の場合、以下のように税率が上昇します。
| 一年間の課税所得 | 税率 |
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円~330万円未満 | 10% |
| 330万円~695万円未満 | 20% |
| 695万円~900万円未満 | 23% |
| 900万円~1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円~4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
さらに、この課税所得には、所得税だけでなく住民税も一律10%で課されます。
この2つの税金により、収入から経費や所得控除を差し引いた最終的な課税所得が1,800万円以上になる年は、その超過分に対し、所得税と住民税を合わせて50%、4,000万円以上の部分があれば55%もの税負担が生じます。
自由診療などで負担が生じる事業税
事業税もまた、所得に対して課される税金の一つです。
ただし事業税では、社会保険診療報酬に基づく所得は非課税とされており、さらに年間290万円までの控除が適用されるため、所得税や住民税ほど負担に感じることは少ない税金といえます。
一方、対象となる所得から290万円を控除した額に対しては、5%の税金が課税されます。
自由診療や物販などによる収益の規模が大きくなってきた際には、事業税の負担も無視できないものになってくるでしょう。
前々年の課税取引により発生する消費税
消費税は、独自のルールで課税対象となる取引が定義されており、その対象となる取引での収入が、前々年において1,000万円を超えると納税義務が発生する仕組みになっています。
この課税対象となる収入に、社会保険診療報酬は含まれません。
そのため、事業税と同様に、すべての開業医に発生する税金ではなく、自由診療や物販などの規模が大きくなると納税が必要になる税金になります。
納税義務が発生した場合は、原則として、取引で受け取った消費税から、経費などとして支払った消費税の差額を計算して納税することになります。
施設や設備を所有しているだけでかかる税金も
施設や設備を個人で所有している場合にも、税金が毎年かかります。
医療関連などの設備のうち償却資産に該当するものには固定資産税(償却資産税)がかかり、不動産(土地・建物)については固定資産税に加えて都市計画税がかかります。
税率は、固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%を基準に、自治体ごとに条例で定められています。
この自治体ごとの税率が、各財産の取得価額から算出された評価額に対して、毎年適用されます。
開業医に効果的な節税対策10選
それでは、開業医の先生方が取り組みやすく、かつ、効果の高い節税対策10選をご紹介します。
特に税負担が重くなりやすい所得に対する税金(所得税など)の節税対策を中心に、消費税や固定資産税(償却資産税)の対策も紹介します。
対策1:概算経費を活用する
所得税や住民税の対象になる課税所得は、収入から経費や所得控除を差し引いた金額となります。
収入から差し引くことのできる経費は、通常、実際に発生した「実額」で計算しなければなりません。
しかし、社会保険診療報酬が5,000万円以下であり、かつ総収入金額が7,000万円以下であれば、「概算経費率」に基づく経費の特例の対象になります。
この制度では、実額の経費に代えて、収入に所定の「概算経費率」を乗じた「概算額」を経費として計上することができます。
実額の経費とどちらが有利になるか(どちらが多くなるか)は比較が必要ですが、概算経費を適用したほうが実額よりも有利になることが多いです。
対策2:経費をこまめに計上する
日頃からこまめに経費を計上し、課税所得を減らすことも節税につながります。
たとえ「概算経費率」を適用できる見込みがあっても、概算経費が常に有利とは限りません。
そのため、実額による経費も、領収書などの書類を保管し、忘れないうちに帳簿に記録しておくことが大切です。
また、経費で節税するには、どのような支出が経費になるのか、経費の「範囲」に関する知識も必要になります。
たとえば、開業前に発生した費用(例:広告宣伝費や人件費など)があれば、「開業費」として繰延資産に計上することで、開業後に償却して経費にできることは、知らなければ計上にしないまま確定申告をしてしまうことでしょう。

実額による経費でも、経費になるものを知っていれば節税する手段はたくさんあります。
なかには、「人材育成に力を入れたい」「設備投資に力をいれたい」といった、開業医としての経営戦略に合わせて実施できる節税対策もあります。
節税や経営支援に関する実績豊富な当事務所にぜひご相談ください。
対策3:所得分散により税率を下げる
所得税は、超過累進税率の仕組みにより、所得が一人に集中するほど税負担が重くなります。
これを回避するために、家族に個人医院の仕事をしてもらい、個人医院から給与を支払うことで、個人医院の所得を家族に分散させる方法があります。
給与を受け取った家族には、給与独自の「給与所得控除」が適用されることも節税に有利に働きます。
対策4:経営セーフティ共済に加入する
「経営セーフティ共済」とは、取引先の倒産に備えて掛け金を積み立て、有事の際には、それまでの掛け金合計の10倍に相当する融資(最大8,000万円)をスピーディに受けられる制度です。
対策5:小規模企業共済・iDeCoに加入する
老後の資産形成に役立つ「iDeCo(イデコ)」や、自営業者の退職金代わりと呼ばれる「小規模企業共済」では、支払った掛け金をすべて所得控除(小規模企業共済等掛金控除)に計上することで、毎年の所得税や住民税の課税所得を減らすことができます。
また、将来に一時金として受け取れば、税負担の少ない「退職所得」として受け取ることが出来る、加入者にとって有利な制度となっています。
現在(令和7年以降)の掛け金の上限額は、小規模企業共済が月7万円で年84万円、iDeCoが月7.5万円で年90万円となります。
この2つは併用(両方に加入しそれぞれに掛け金を支払うこと)が可能です。
対策6:設備投資の優遇税制を活用する
節税効果のある設備投資の制度も、条件に該当する範囲で積極的に利用したいところです。
代表的な制度に、中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制があります。
これらの制度は医療機器が対象外となるため、開業医の節税対策として見落とされがちです。
しかし、たとえばレセコンの導入時などシステム関連の投資などは、制度の対象となる「70万円以上のソフトウェア」として利用できることがあります。
これらの税制では、減価償却費を通常より多く計上できる「特別償却」や「即時償却」と、その年の所得税そのものを減額できる「税額控除」を選べます。
対策7:30万円未満の資産を購入する
10万円以上の機械や備品など事業のための資産を購入すると、通常は一度に経費にすることができず、その耐用年数にわたり「減価償却費」として少しずつ経費にしていく必要があります。
つまり、10万円以上の資産は、経費にできるまでに時間がかかるのです。
しかし、青色申告をしている場合、30万円未満の資産まで、使用開始年にその全額を経費として計上できる特例があります(年300万円が上限)。

個人開業医の場合、所得が高くなるほど適用される税率も上がります。
たとえば、その年の所得が想定以上に増え、対策ができないまま年末を迎えてしまったような時、買い替えが必要な30万円未満の備品を購入し、この特例で経費にする「駆け込み」的な活用術もおすすめです。
対策8:消費税は簡易課税を検討する
消費税の課税事業者になることが分かったら、「簡易課税」の選択を検討しましょう。
通常、消費税の納税額は、受け取った消費税から、実際に支払った消費税を差し引いて計算します。
これに対して簡易課税を選択すると、支払った消費税を実額ではなく、業種ごとに定められた「みなし仕入率」に基づいて計算することができ、納税額が少なくなるケースがあります。
制度の適用には、あらかじめの届け出が必要です。
また、実際に適用できるのは、前々年の課税売上高が5,000万円以下である年に限られます。

「簡易」という名称を見ると、つい「簡単に申告できる」と想像してしまいます。
しかし、事務負担はあまり変わりません。
簡易課税でも、各取引の事業区分を正確に区別して経理を行う必要があります。
消費税の経理や申告でご不安があるときは、当事務所にご相談ください
対策9:償却資産税は取得・処分の時期や償却方法を工夫する
償却資産税の課税対象になるものは、毎年1月1日に保有している資産です。
そのため、もし新たに資産を購入する場合は、その日より後にすれば初回の発生を一回遅らせることができますし、同じ理由で、使用していない資産を処分する際も、その日より前に行えば、最後の1回の負担を避けられる仕組みとなります。
また、20万円未満の償却資産を取得した際には、通常の減価償却や先ほどの30万円未満の特例のほかにも、「一括償却資産」として、3年で均等償却する方法を選ぶことが可能です。
この「一括償却資産」の対象とした資産は、償却資産の申告対象になりません。
小さな節税策ではありますが、すぐに全額を経費にしなくても問題がない場合は、積極的に活用したい方法です。
対策10:医療法人化を検討する
所得税の税負担が大きくなってきたと感じたときに検討したい節税対策が、個人医院の法人化です。
個人開業医の場合、所得が増えるにつれて所得税の負担が重くなります。
しかし、法人化すれば、個人医院の所得は所得税ではなく「法人税」の対象となります。
法人税の税率は23.2%(800万円以下の部分は15%)であり、所得税の高額部分(最大45%)に比べて低いため、個人医院の所得が大きくなるほど、法人化による節税効果も高くなります。
また、家族に給与を支払う所得分散の対策も、法人化すれば自分自身にも給与(役員報酬)を支払えるようになるため、より柔軟な配分で節税ができるようになります。

現状によっては、一般的に言われている目安より所得が少なくても、法人化で節税効果を得られる場合があります。
一方で、法人化による社会保険料の負担増や、医療法人の設立や運営コストなど、個人開業医にはない新たな負担も一緒に検討しなければ、医療法人化で後悔することになりかねません。
どの方法が今一番良い対策になるのか、当事務所は総合的に判断してご提案します。
お気軽にご相談ください。
まとめ
【開業医にかかる税金の種類】
・所得税
・住民税
・事業税
・消費税
・固定資産税(償却資産税)
【節税対策10選】
・概算経費を活用する
・経費をこまめに計上する
・所得分散により税率を下げる
・中小企業退職金共済・経営セーフティ共済に加入する
・小規模企業共済・iDeCoに加入する
・設備投資の優遇税制を活用する
・30万円未満の資産を購入する
・消費税は簡易課税を検討する
・償却資産税は取得・処分の時期や償却方法を工夫する
・医療法人化を検討する

いかがでしたでしょうか。
今回は、開業医の先生方の節税について解説しました。
これらの対策は、どの開業医の先生がやっても同じ効果が得られるわけではありません。
収入の規模や構造、家族構成などによって、効果の出方は異なります。効率よく節税を行うには、今の状況に合った方法を優先的に実施することが大切です。
当事務所では、開業医の先生方の節税対策や税務会計に関する業務(記帳・決算・申告等)はもちろんのこと、医療法人化やその運営など医業経営のための総合的なご支援を、他士業と連携しながら行っております。
お気軽にご相談ください。
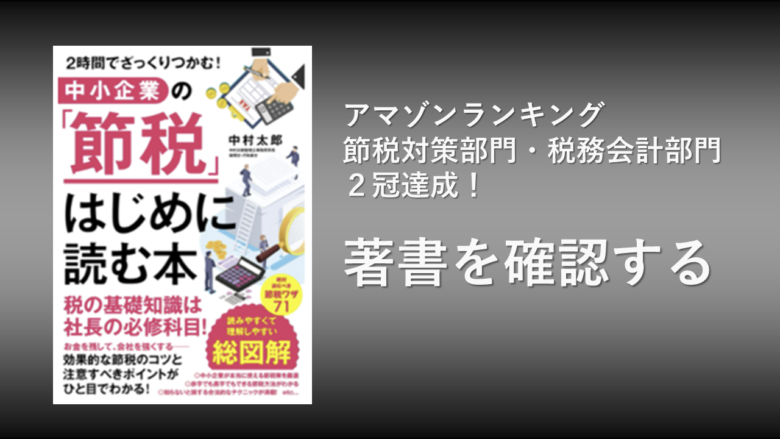


















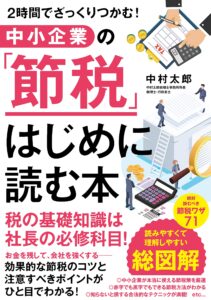

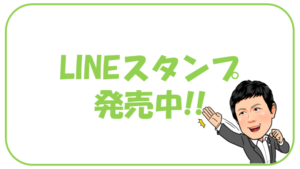
今回は、開業医の先生のための節税対策をご紹介します。
個人医院を開業された今、想像以上の納税額に戸惑っていらっしゃる先生も多いのではないでしょうか。
なかでも特に負担が気になる税といえば、「所得」に対する複数の税金だと思います。
一年間の課税所得が1,800万円を超えると、その超過分にかかる税率は、所得税や住民税を合わせて50%にもなります。
「忙しい割に手取りが増えなくなったな」と感じると、働くモチベーションにも悪い影響を及ぼしかねません。
そこで、正しい節税対策が必要です。
働いた分をきちんと自分の成果として残すために、そして、手元に残った資金で、さらに充実した医療を提供するために、節税対策は開業医の先生にとって必須の取り組みといえます。
今回は、開業医の先生に知っていただきたい10の節税対策をわかりやすく解説します。