そもそも、税務調査とは?
税務調査とは、納税者が提出した法人税、所得税、消費税、相続税や贈与税などの申告書の内容に誤りがないかどうか、税務署や国税局が確認するために実施するものです。
税務調査で誤りが発覚すれば、その部分を正した修正申告を提出してもらうなどし、不足していた納税額の差額や、それに対する加算税などが追徴されます。
中小企業や個人事業主に対して行われる調査の多くは「任意調査」と呼ばれるものであり、原則として事前に通知されたうえで実施されます。
税務調査による追徴課税はどのくらいある?
国税庁によると、令和5事業年度に実施された法人税の実地調査は5.9万件でした。
そのうち非違のあった件数は4.5万件ですので、全体の76%の法人で何らかの誤りが指摘されていることがわかります。
税務調査に入られたら、無傷で済まないことがかなり多いということです。
なお、この年度の法人税の調査において追徴された税額は、全体で2,102億円であり、実施調査1件あたりに換算すると358万円(地方法人税や加算税を含む)となります。
(参考)国税庁:令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/hojin_chosa/index.htm
税務調査の種類「任意調査」と「強制調査」の違い
税務調査には、「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。
任意調査とは、納税者の理解を得ながら任意で実施される税務調査のことをいいます。調査を担当するのは、多くの場合、管轄の税務署職員です。
原則として事前に通知されたうえで、過去3年分ほどの税務申告に対し、2日ほどかけて会社などの現地で調査が行われます。
一方、巨額な脱税が疑われるケースに対しては、国税局の査察部による強制的な捜索・差押えが行われることもあります。
裁判所の令状に基づき、事前連絡なく会社や自宅などの捜索が強制的に行われ、発見された証拠物品は押収されます。
天井裏の脱税資金まで見つけてしまうような、非常にダメージの大きいものとなります。
法人に対する任意調査の件数は、例年6万件ほどであることに対し、査察による調査は年間150件ほどに過ぎません。
このことから分かるように、多くの企業が受ける調査は、前者の「任意調査」です。
多くの経営者が「税務調査が来た」と言っているのは、「任意調査」を指していることが一般的なのです。
「任意調査」なら拒否できる?
税務調査が「任意」と聞くと、調査を拒否するのも自由なのではないかと思われるかもしれません。
しかし、任意調査であっても、税務署職員には帳簿や資料の提示を求める「質問検査権」が法律により認められています。
そして、これに基づく答弁をしなかったり、正当な理由なく帳簿書類などの提出に応じなかったりする行為には、罰則が設けられています。
つまり、調査の形式としては「任意」であっても、税務調査の対象に選ばれたら、調査そのものは甘んじて受け入れるしかないのです。
税務調査における税理士の立会いとは
税務調査には、税理士が立会うことが認められています。しかし多くの方はきっと、「税理士がいたからといって、どうなるんだ」と思われるのではないでしょうか。
税務署をはじめとする税務当局の調査官は、日々多数の申告書や帳簿書類を精査しています。税務に関する知識も経験も、一般の納税者とは比較にならないほど豊富であり、特に「ミスを見つけ、指摘し、認めさせる」ことに関しては百戦錬磨と言ってよいでしょう。
そのような相手を前に、いくら「余計なことは言わない」と決意していても、実際の調査の場では緊張から答えなくていいことまで答えたり、提示しなくてよい資料まで見せてしまったりすることは珍しくありません。
このように税務調査では、どうしても調査官側の主導になりやすく、納税者側に不利になりがちです。 そこで、税理士が立会うことに大きな意味があります。
税理士は、納税者の「税務代理人」として立会うことができるため、単に調査の場に同席するだけではなく、調査官からの質問に対し、企業や個人事業主に代わって答弁することができます。
この強力な代理権限により、調査官の見解に法の趣旨を踏まえて応答するため、納税者が一方的に不利な立場に置かれる事態を防ぐことができるのです。

当事務所では、まずクライアント様としっかり打ち合わせを行い、調査で見られやすいところと予想されるやりとりを事前に共有いたします。
そして、当日はクライアント様が一方的な指摘を受けて不利な立場にならないよう、調査官に毅然と答弁いたします。税務調査についてご不安のある方はこちらをご覧ください。
税務調査に税理士を立会わせるメリット
それでは、税理士に税務調査の立会いを依頼した場合、具体的にどのような流れで行動し、どのようなメリットを納税者にもたらしてくれるのでしょうか。
税理士に立会いを依頼すると、以下のようなメリットが得られます。
事前に打ち合わせができる
前述のとおり、任意で行われる税務調査であれば、原則として事前に通知されます。そのため、税理士に税務調査の立会いを依頼すると、事前に打ち合わせの機会を設けることができます。
税務調査を受ける納税者にとっての不安は、「調査官から何を尋ねられるのか分からない」という点にあるはずです。
実際、調査当日には帳簿や書類を確認した調査官から、さまざまな質問が投げかけられます。なかには、質問の意図がつかめず、どう答えるべきか判断に迷うものもあるでしょう。
税理士が税務調査に立会う場合、事前に機会を設けて帳簿書類や申告内容をチェックし、不備や指摘されそうな点がないかを確認します。
そのうえで、税務調査時の質問にしっかりと答えられるよう打ち合わせを行うため、納税者にとっては大きな安心となります。
法的観点からの説明が可能になる
税務調査の当日は、税務調査官が、法律で認められた質問検査権にもとづき、帳簿や書類、申告内容に関する答弁を求めてきます。
しかし、調査官と納税者では、税務や会計に関する知識に差があります。
そのような二者のみでやり取りを行うと、法令解釈や会計基準に関わる論点で、誤解や対立を招くことがあります。
また、本来ならそれほど問題のない処理であっても、納税者側の説明不足で不利な判断を受けたり、逆に余計な説明をしたことによって過剰に疑いを向けられたりすることもあります。
税理士が立ち会えば、調査官に税務上の理論で応答できるため、調査官との誤解や対立を防ぎ、過剰な追徴課税のリスクを回避することができます。
調査内容の妥当性を確認し、不当な指摘を防ぐ
税務調査官も人間である以上、その経験や判断力には個人差があります。
しかし、調査官が行き過ぎた指摘を行ってきたとしても、納税者側にはそれが妥当なのかそうでないのか判断する材料がないため、言いなりになるしかありません。
税務調査に精通した税理士が立ち会えば、調査官の指摘が妥当かどうかを判断し、指摘が行き過ぎであると感じた時は、適切に反論します。
この対応により、調査を一方的に進められることや、調査官の言いなりになる状態を防ぐことができます。
調査後の対応がスムーズになる
税務調査の結果から、修正申告が必要になる場合があります。
この場合、税務調査に立会った税理士がいれば、調査結果と整合性のとれた修正申告まで依頼することが可能です。
こうした手続きを任せることで、憂鬱な気持ちを切り替え、早く通常業務に戻ることができます。
税務調査に立会わせる税理士の選び方
税務申告をご自身で行っている方や、顧問税理士がいても何らかの事情で税務調査に立ち会ってもらえない場合には、新たに対応可能な税理士を探す必要があります。
では、そのようなとき、どのような基準で税理士を選べばよいのでしょうか。
ここでは、税務調査の立会いを依頼すべき税理士を選ぶためのポイントを紹介します。
税務調査の立会いに対応している税理士
まず大前提として、税務調査の立会いに対応している税理士を選ぶ必要があります。
これは当然のことのように思えるかもしれませんが、すべての税理士が税務調査の立会いに対応しているわけではありません。
顧問先以外の税務調査には立ち会わない事務所もありますし、無申告であるなどの事情があると、対応を断られることもあります。
まずは候補となる税理士事務所のホームページ等を確認し、税務調査の立会いが可能か、可能であれば料金体系が明示されているかどうかをチェックしましょう。
税務調査の経験が豊富である税理士
税務調査は、机上の理論だけで乗り切れるものではなく、現場での経験が不可欠です。
特に、調査官との間で見解が分かれた時は、経験がものをいいます。
法的根拠をもって理路整然と応答できる胆力を備えつつ、その一方で、意固地にならず納税者の追徴税額を最小限に抑えるために交渉できる柔軟性も求められます。
税務調査の現場では、税理士のこうした対応力・判断力が、重い追徴課税から納税者を守ることにつながっています。
したがって、立会いを依頼する税理士は、税務調査に関する経験が十分にある人物を選ぶことが重要です。
税務調査のリスクを下げられる税理士
日ごろの税務申告の段階で調査リスクを下げる方法として、税理士法第33条の2に基づく「書面添付制度」があります。
これは、法人税などの申告書に、税理士がその確認状況などを記載した一定の書面を添付する制度です。
わかりやすく言えば、「この申告書は私(税理士)が確認しました」という「品質保証」のような役割を果たすものです。
この書面添付が行われた申告については、すぐに現地での税務調査が行われるのではなく、まずはその税理士に対して意見聴取を行うことが義務付けられています。
この意見聴取によって税務署側の疑問が解消されれば、現地での調査が行われないこともあります。
つまり、書面添付を積極的に行う税理士を選べば、税理士と税務署のやり取りで調査が済むケースもあるのです。
将来的に税務調査リスクを減らしたいと考えるなら、書面添付制度に対応している税理士を顧問税理士に選ぶ視点も重要といえます。
まとめ
税務調査には、税理士に立会いを依頼することで、事前準備や調査時の対応、調査後の修正申告まで一貫したサポートが受けられます。
専門知識と経験を持つ税理士が立ち会うことで、不当な指摘や過剰な追徴課税のリスクを防ぎ、調査を有利に進めることが可能になります。
当事務所では、調査前の打ち合わせから当日の対応、調査後のサポートまで、納税者の皆さまに寄り添った対応を行っております。
税務調査に不安を感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。

税務調査は、どれほど気をつけて申告していても不安を感じるものです。しかし、事前準備や専門家の立会いによって、安心して冷静な対応をすることができます。
本記事でご紹介したように、調査の対応力はもちろん、日ごろの申告段階からリスクを下げられる税理士の存在は、とても大きな支えになります。
当事務所では、税務調査に関する事前相談から立会い、書面添付制度の活用まで、万全の体制でサポートしています。
不安を抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
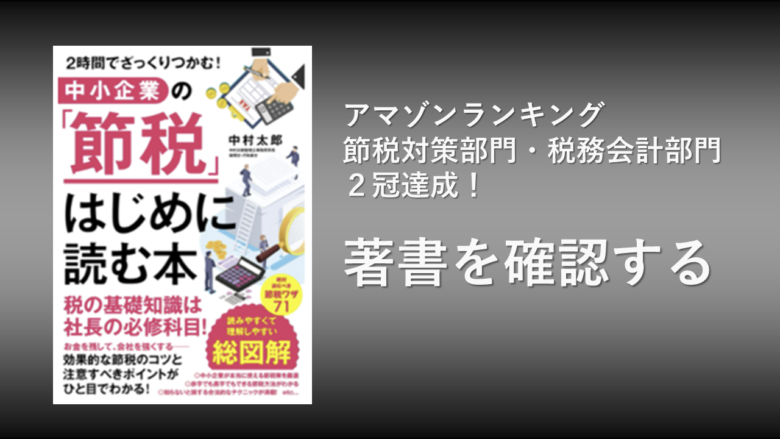





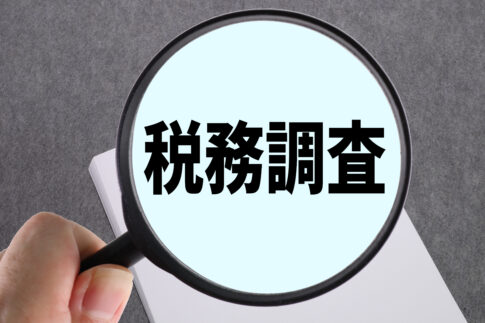

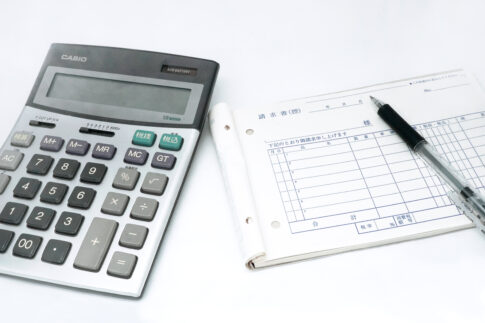




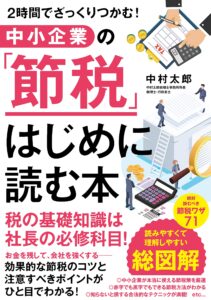

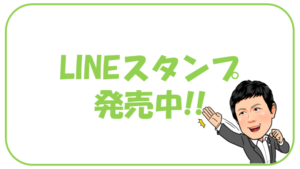
こんにちは。税理士の中村太郎です。
今回は税務調査について。
税務調査の通知が届いたとき、多くの方が不安や戸惑いを感じます。「何を準備すればいいのか」「税理士に立会いを頼むべきか」と悩まれる方も少なくありません。
この記事では、税務調査の基本から、税理士が税務調査に立ち会うことのメリット、立ち会う税理士の選び方までをわかりやすく解説します。