クリニックにおける経営計画の必要性
まずは、クリニックにおける経営計画について、わかりやすく解説します。
そもそも経営計画とは
経営計画とは、経営理念やビジョン、経営戦略に基づき、その組織が将来あるべき姿(目標)にたどり着くための道筋を書き表したものをいいます。
つまり、経営計画とは現状から将来への道しるべとなる計画を指すのですが、作成する際には「将来の姿」からの逆算となります。
簡単な例で、クリニックの経営計画を策定するイメージをつかんでみましょう。
・その地域にどのような患者のニーズがあるのか
・それに対し、ご自身はどのようなクリニックでありたいか
・そうしたクリニックになるには、どのような設備や人材が必要か
・その設備や人材を確保できるクリニックの経営をするには、どのくらいの利益が必要か
・その利益を得るには毎月どのくらい患者数が必要か
大まかではありますが、このように経営計画は、まずは院長がその地域で実現したいクリニックの将来像を描き、それを実現するために「今からすべきこと」を逆算することで策定していきます。
経営計画の種類
経営計画は、計画の対象期間によって以下の3つに分けられます。
・短期経営計画
1年の経営計画。対象期間が短いため、実現可能な計画を作成しやすい。
・中期経営計画
3年~5年の経営計画。長期的なビジョンを実現するための中間地点となる計画。
・長期経営計画
5~10年の経営計画。将来あるべき姿の実現に向けた計画。
短期経営計画は対象期間が短く、比較的作成しやすい計画ですが、それだけではクリニックの経営理念やビジョンが希薄になりがちです。
そのため、長期経営計画を策定し、その中間目標として中期経営計画を設定することで、短期目標の達成を積み重ねながら、将来の目標へと着実に近づくことができます。
経営計画と事業計画の違い
経営計画と似た言葉に「事業計画」があります。
同義で使用されることもありますが、一般的に経営計画とは、経営理念やビジョン(将来像、目標)といった、その組織のあるべき姿を達成するための計画全体を指します。
一方、事業計画とは、経営計画で定めた戦略や目標を前提とした行動計画を指す場合が多く、経営計画に包括されるものとなります。
融資の申し込みや補助金の申請などの際に提出が求められるものも「事業計画」ですが、事業計画を作成する際にも、まずは組織としての経営計画を策定しておくことにより作成を円滑に進めることができます。
なぜクリニックに経営計画が必要なのか
医業は一般的に参入障壁の高い業種ですが、外部要因による影響を受けないわけではありません。
クリニックの収益の多くは、自由に価格設定ができない診療報酬に依存しています。
そのため、人口の減少や競合の増加によって患者数が減少すると、収益の低下に直結します。
さらに、多くの競合クリニックが自院の強みを打ち出し、差別化を図ろうとしている中で、何の対策も講じなければ、収益は減少する一方となる可能性があります。
こうした事態に備えるためには、外部環境に左右されない強固な経営基盤を構築することが必要です。
それを実現するには、経営環境の分析を行い、課題に対する具体的な戦略を立て、それをクリニック全体で実行することが欠かせません。
経営計画を策定し、その実行と進捗管理を継続することで、クリニックは将来あるべき姿に着実に近づいていくことができます。
クリニックが経営計画を策定するメリット
クリニックが経営計画を策定することには、さまざまなメリットがあります。
クリニックの将来像を明確にできる
経営計画を立てる際には、クリニックの経営理念やビジョンを決め、将来のクリニックの姿を明確にすることが欠かせません。
経営計画を策定することは、クリニックが目指す方向性を整理し、具体的な目標を明確にするチャンスとなります。
経営課題を分析し、より強い経営基盤を築ける
クリニックの経営は、地域人口の変化や競合医院の増加、診療報酬の改定など、外部要因による影響を受けます。
そのため、経営計画を策定する際には、外部環境や自院の強みを分析することが欠かせません。
こうした分析を踏まえ、経営課題とその対策を明確にし、クリニックの強みを活かした経営戦略を立てることで、他院と差別化された、より強い経営基盤を築くことができます。
スタッフの行動指針となる
クリニックの経営計画は、スタッフと共有することが重要です。計画を共有することで、スタッフのモチベーションが向上し、一人ひとりが同じ理念のもとで行動できるようになります。
その結果、院内の雰囲気や患者対応の質が向上し、患者に「感じのいい先生と看護師がいるクリニック」「いつも明るくてきれいな院内」といった好印象を与えることにつながります。
資金調達にも役立つ
金融機関への融資の申し込みや補助金の申請では、事業計画の提出が求められます。
提出先によっては、定められた様式に合わせて作成しなければなりませんが、経営計画をしっかりと策定しておけば、こうした事業計画の作成にもスムーズに対応できます。
クリニックの経営計画の作成手順
経営計画の実行と管理について詳しく解説してまいります。
経営理念・ビジョンを明確にする
クリニックの経営理念や将来のビジョン、必要であればバリュー(価値観)やミッション(使命)を明確にします。
これらを明確にすることで、スタッフの意識がまとまり、患者からの信頼を得ることにもつながります。
経営戦略を策定する
経営理念やビジョンを達成するために、具体的な戦略を策定します。
クリニックを取り巻く外部環境と内部環境をSWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)などを活用して客観的に評価し、そこから洗い出した課題に対する戦略・目標を打ち出していきます。
経営計画を策定する
経営戦略や経営目標をもとに、具体的な経営計画を立てます。計画には、以下の3つの要素を含めます。
・行動計画
経営戦略を実現するための具体的な行動計画です。
診療方針や患者対応、院内環境の整備など、クリニック運営に関わる具体的な施策を決定します。
・利益計画
目標とする収益と費用を管理するための計画です。
収益の成長と、それに伴い増大するコストを管理しながら、安定した利益を生み出します。
・資金計画
利益とは別に、資金の流れを管理するための計画です。
資金調達や借入の返済計画を策定し、安定した財務基盤を築きます。
経営計画を立てた後に重要な「実行」と「管理」
経営計画を策定した後は、計画の実行とその進捗状況の管理が不可欠です。
経営計画を立てただけでは成果にはつながらず、確実に実行し、それを管理することが求められます。
ここでは、「実行」と「管理」に分けて、それぞれのポイントを解説します。
経営計画の「実行」のポイント
経営計画は、スタッフに周知することが欠かせません。
その際、一人ひとりの行動変化につながるよう、具体的な指示を行うことが重要となります。
ポイントは、医師や看護師、技師、事務員など、それぞれが自身の職務の中で実行しなければならないことを分けて伝えることです。
院長の手元にある計画書の内容をそのまま全員に伝えると、情報量が多すぎて具体的な行動につながりにくくなります。
それぞれの業務に合わせて整理し、わかりやすく伝えることで、スムーズな計画の実行につながるでしょう。
経営計画の「管理」のポイント
経営計画を実行中は、計画と実績を照らし合わせ、進捗状況を把握する必要があります。
特に、利益計画に基づく予算と実績の管理は不可欠であり、できれば毎月実施することが望ましいです。
計画との差異が生じた場合は、その要因を正確に把握し、必要に応じて改善策を講じることがポイントになります。
たとえば、毎月の収益予測を「予想患者数×予想単価」で算定していたところ、予定よりも収益が伸び悩んだ場合、まずは何が足りなかったのかを分析します。
もし原因が予想患者数に到達しなかったことだとわかった場合、さらにそれが、再来院が減少したのか、新規の来院が増えていないのかといった要素で分析し、原因に応じた対策を講じます。
クリニックの経営計画における注意点
ここからはクリニックの経営計画における注意点について解説していきます。
財務会計や経営の知識が必要となる
経営計画の精度は、作成者の財務会計やクリニック経営に関する知識と経験によって大きく左右されます。
知識や経験が不足していると、計画がクリニックの実態とかけ離れ、現実には実行不可能な、いわゆる「絵に描いた餅」になりがちです。
実現できない目標は、いずれ管理が困難になり、結果としてスタッフの士気を下げる要因にもなってしまいます。
管理不足で計画が無意味になることも
経営計画は策定して終わりではなく、予算と実績の管理を継続することが不可欠です。
予算と実績の数字に乖離が生じた際、どのような対策を講じるべきか判断できなければ、管理が行き届かなくなり、計画自体が形骸化してしまいます。
こうした管理は、一般的にPDCAサイクル(Plan・Do・Check・Act)を用いて、検証と対策を繰り返します。
しかし、十分な時間や担当者を確保できない場合、計画の管理が難しくなり、結果として計画そのものが意味をなさなくなることがあります。
「分析をやりすぎる」ケースも
経営は学べば学ぶほど奥が深く、活用できる分析手法も多岐にわたります。
さまざまな情報に触れることで、現状の問題点をさらに細かく分析した経営計画を策定できるようになるでしょう。
しかし、分析をやりすぎると選択肢が無数に増えていき、最終的には決断すべき事項が多くなりすぎて何も決められなくなるという状況に陥ることがあります(いわゆる「分析麻痺症候群」)。
机上の経営分析だけでなく、医療現場の実態を見ながら、必要な分析とその対策をバランスよく選別して進めていける「経験」も重要なのです。
まとめ
クリニックの経営を安定させ、将来の成長を実現するためには、明確な経営計画の策定と、その継続的な管理が不可欠です。
しかし、計画を作成するには財務会計や経営の知識が求められ、さらに管理には相応の時間と手間がかかります。
当事務所では、クリニックの経営支援に特化した専門家が、経営計画の策定から実行支援、管理までをしっかりとサポートします。
・クリニックの経営課題を分析し、最適な戦略を提案
・資金繰りや利益計画の精度を高め、安定した経営を実現
・管理の負担を軽減し、スムーズな計画の運用を支援
「経営計画を作りたいが、何から始めればいいかわからない」「作った計画をどう管理していけばいいのか不安」。
そのようなお悩みをお持ちの院長先生は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

いかがでしたでしょうか。
今回はクリニック経営を成功に導くため、経営計画の作成手順・管理のポイント・注意点について解説いたしました。
適切な経営計画を立て、確実に実行するためには、専門的な知識と経験を持つパートナーのサポートが大きな助けになります。
クリニックの経営についてお困りのお客様はぜひお気軽にご相談ください。
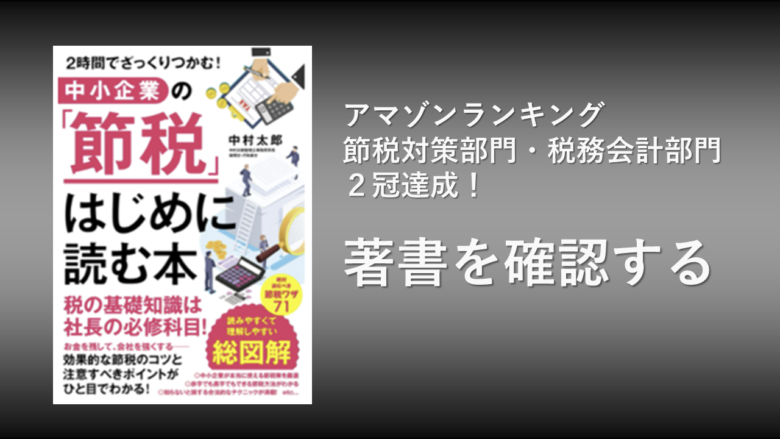


















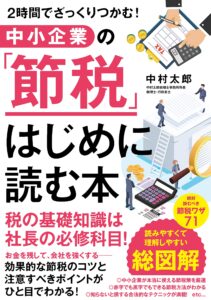

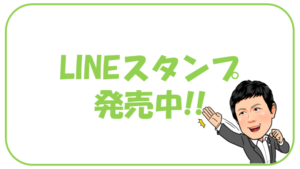
まいど!西新宿の税理士 中村です!
クリニックをはじめとする医療業界は、人口減少や競合の増加の影響により、厳しい経営環境に直面しています。
成り行き任せの経営では改善が難しくなっており、クリニックの経営にも差別化を意識した計画的な運営が求められる時代となりました。
こうした状況を打破するには、経営計画を策定することが有効です。
自院の方針や成長戦略を明確にすることで、持続的な成長を実現することができます。
本記事では、クリニックにおける経営計画の必要性と、その策定のメリット、具体的な作成手順について詳しく解説します。
是非ご一読ください!