医師が不動産投資を行うべき理由
医療法人化とは、院長が個人で運営する診療所などを、法人格を持つ組織に移行することを指します。
全国の医療法人の数は年々増加し続けており、2015年3月末の調査では、5万件を超えたことが確認されています。
また、そのおよそ8割は「一人医師医療法人」(医師または歯科医師が常時1人または2人勤務する診療所を開設する医療法人)に該当し、多くの個人の医師が、医療法人を設立していることがわかります。
医療法人化のメリット
個人クリニックが医療法人化することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。
ここでは、5つの代表的なメリットについてご紹介します。
節税効果がある
個人クリニックの場合、その利益は個人の「事業所得」として、所得税などが課税されます。
所得税には、所得の高額な部分に高い税率が適用される超過累進税率が採用されています。
税率は、5%から最大45%です。
これにより、事業所得(収入-経費)が2,000万円を超えると、一般的にそこからの増加分には、住民税なども合わせて50%を超える税負担が生じる見込みとなります。
そのため、個人クリニックのまま所得を拡大すると、「前より忙しくなったけれど、その割に手元に残るキャッシュはあまり伸びないな」と感じる時期が訪れるはずです。
一方、医療法人化すれば、その所得は医療法人の所得となり、所得税から法人税の対象になります。法人税の税率は、基本的には一律23.2%であり、他の税を合わせても、所得に対する税負担はおおむね30%~35%程度になります。
つまり、所得の大きい個人クリニックほど、医療法人化によって、毎年の税負担を軽減できるのです。
医療法人化には他にも、院長やご家族に報酬を支払うことで、さらなる節税効果が見込めます。また、将来の事業承継や退職の際にも、個人より節税しやすい面があります。

当事務所では、医療法人化による節税シミュレーションを行い、どのくらいキャッシュが増えるのかをご説明します。
所得税と法人税の税率差だけで節税効果があるように見えますが、実際は、いくらの報酬を院長が受け取られるか、それにより、社会保険料はいくら増加するかといった変化を踏まえて検討する必要があるからです。
ご自身のクリニックの場合はどうなるのか気になられた方は、ぜひご相談ください。
事業展開の選択肢が増える
医療法人化によって、事業展開の選択肢を広げることもできます。
個人クリニックの場合は一つの拠点でしか医療機関を運営できませんが、法人化することにより、複数の分院や介護事業を運営できるようになります。
また、節税効果のメリットにも通じる話なのですが、個人のままでは所得が増えるほど税負担も重くなることから、「これ以上、頑張って医院を大きくしても、税金が増えるだけだ」という、働き損のような気持ちになりがちです。
医療法人化によって税負担を抑えられるようになれば、こうした気持ちもなくなり、新しい事業展開に前向きになれることでしょう。
社会的信用性が向上する
医療法人化には、医療法に基づく都道府県の認可が必要であり、法人化した後もその監督を受け続けます。こうした厳格な制度から、医療法人化には、一般的に社会的信用性を向上させるメリットがあります。
例えば、金融機関への融資の申し込みや、優秀な人材確保の面などで、有利に働くことが期待できます。
資金管理がしやすくなる
個人クリニックでは、収入から経費を差し引いた残りは、院長の判断で自由に使うことができます。
便利ではありますが、その反面、生活に使える資金がわかりづらく、家計と事業の資金が混ざってしまいがちです。
医療法人化すると、家計と事業の資金は明確に分かれます。
これにより、生活に使える資金と事業で使える資金を別個に把握できるようになるため、設備や人事など大きな投資判断も、自信を持って行えるようになります。
事業承継がスムーズになる
医療法人化により、事業承継もスムーズに進められるようになります。
個人クリニックで事業を次世代に引き継ぐには、院長交代に伴い、廃業と新規開業の手続きが必要となります。
また、事業用資産を後継者に移転させる際に、多額の贈与税が発生することもあります。
一方、医療法人の場合は、理事長の交代手続きのみで事業承継が完了します。
さらに、「持分なし」の医療法人であれば、出資した持分に対する相続税や贈与税の課税も行われません。
医療法人の出資持分については、こちらの記事で詳しく解説しています。
医療法人化のデメリット
医療法人化には、多くのメリットがある一方で、デメリットともいえる注意点があります。
ここでは、法人化によって生じる負担やリスクについて整理します。
設立するための手続きが難しい
医療法人の設立には、都道府県の認可を必要とします。
申請できるチャンスは年2回ほどしかなく、タイミングがシビアとなります。
しかも、その際にはさまざまな書類を提出しなければならず、かなり前から準備を始めていなければ間に合いません。
さらに、申請を行ってから医療法人として活動ができるようになるまでには、認可のための審査や認可後の手続きを含めて、1年近くかかります。
このように医療法人化は、法人を設立するまでの手続きが難しく、多忙な先生方が気軽に取り組めない要因といえます。
東京都での設立スケジュールについては、こちらの記事で解説しています。

医療法人の設立申請書類の準備は複雑で時間がかかります。当事務所ではこれまで医療法人化をご支援してまいりました。
「何から始めればいいかわからない」という状態でも心配いりませんので、お気軽にご相談ください。
事務負担が増える
医療法人化すると、個人クリニックでは必要なかったさまざまな事務負担が生じます。
例えば、社員総会・理事会の開催やその議事録の作成、都道府県への毎年の事業報告、決算のたびに行う法務局への資産の総額の変更登記、そして法人税や法人事業税等の税務申告などです。
これらはすべて法令に基づく義務ですので、欠かさず行わなければなりません。

医療法人の運営には、多くの事務負担が生じます。
当事務所では、税務に関わるご支援はもちろん、それ以外の医療法人に必要な手続きを一貫してサポートし、先生が診療に専念できる環境づくりをお手伝いしていますので、安心してお任せいただけます。
社会保険への加入義務が生じる
医療法人化すると、社会保険への加入が必要となります。それによって、院長を含めた役員・従業員の健康保険や厚生年金保険料の負担が新たに発生します。
節税効果を求めて医療法人化を検討する際には、この社会保険料の負担増も一緒に考えることがポイントです。
もっとも、これは、老後の年金増加や従業員の福利厚生につながる、単なるコスト以上の効果もあります。
金銭的な負担は増えるものの、将来の安定や職員の安心感につながる投資と考える視点も大切です。
法人の資金を自由に使えなくなる
個人クリニックの場合、収入から経費を差し引いた残りを、院長が自由に使うことができました。
これに対して医療法人の場合は、法人の財産と個人の財産は明確に区別されるようになり、院長であっても自由に使うことはできません。最初は不便さを感じることもあるでしょう。
しかし、これにより、事業として使える資金が明確になるため、設備投資や人材採用などの事業判断がしやすくなる側面もあります。
医療法人化を検討すべきタイミング
医療法人化をいつ実行するのか、そのタイミングに迷われる先生も多いかと思います。
クリニックの経営状況や今後の展望によって最適な時期は異なりますが、以下のような状況があれば、法人化を検討する目安になります。
税負担が気になり始めたとき
個人クリニックでは、所得税の超過累進税率により、所得が増えるほど税負担が重くなります。
税負担が気になり始めたときは、医療法人化による節税効果をシミュレーションしてみましょう。

当事務所では、どのくらいの収益で医療法人化することがベストであるかもご提案いたします。税負担が気になっている先生方は、お気軽にご相談ください。
概算経費が適用できなくなったとき
社会保険診療報酬(経費を差し引く前の額)が5,000万円を超えるクリニックや、自由診療報酬を含めた総報酬が7,000万円を超えるクリニックもまた、医療法人化を検討すべきタイミングにあるといえます。
この水準を超えると、「概算経費」の特例が適用できなくなり、経費を実額で計上しなければなりません。その結果、税負担が急に重くなるケースが多いためです。
事業承継を検討しているとき
後継者への事業承継を意識し始めている先生も、医療法人化を検討するタイミングにあるといえます。
個人クリニックでは、院長の交代に伴い、廃業と新規開業の手続きが必要となりますが、医療法人であれば、理事長の交代のみでスムーズに承継することができます。
まとめ
この記事では、医療法人化のメリットとデメリットを主に解説しました。
医療法人化には、節税や事業承継などに大きなメリットがある一方で、手続きの複雑さや事務作業の増加など、負担が大きくなる部分も存在します。
当事務所では、先生方のクリニックが医療法人化によりどのくらいのメリットがあるのかを確認した上で、医療法人化の手続きやその後の運営をご支援し、先生方が安心して医療に専念できる環境づくりをお手伝いします。
まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

いかがでしたでしょうか。
医療法人化は、単なる節税手段にとどまらず、将来の安定した経営や事業承継にもつながる重要な選択肢です。
ご自身のクリニックにとって最適なタイミングや方法を一緒に検討してみてはいかがでしょうか。
ご興味のある方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
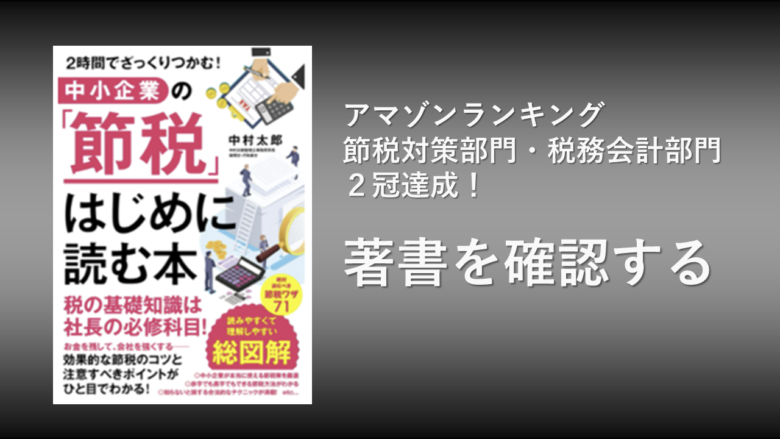


















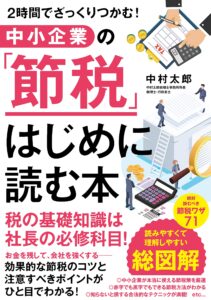

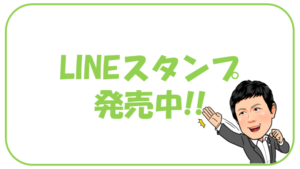
まいど!西新宿の税理士 中村です!
今回は【医療法人化のメリット・デメリットや法人成りのタイミングや注意点】について、ご紹介いたします。
クリニック経営が軌道に乗り始めた医師の先生の中には、医療法人化を検討し始めている方もいらっしゃるかもしれません。
医療法人化には、節税や事業承継のしやすさといった多くのメリットがありますが、その一方で、事務負担の増加といったデメリットも存在します。
この記事では、医療法人化を検討されている先生方に向けて、法人化すべきかどうかを判断するためのメリットとデメリットをわかりやすく解説します。