個人事業主とは
個人事業主とは、法人を設立せずに、個人で事業を営む人をいいます。いわゆる自営業者のことです。個人事業では、何をするにも個人が主体になります。たとえば、融資を受けるときの金銭消費貸借契約は、個人と銀行の間で締結します。
人を雇うときの労働契約も、事業主である個人と、従業員個人との間で締結します。これらに伴う権利や義務、責任は、もちろんすべて個人に帰属します。
個人事業を始めたときは開業届を提出する
個人事業を始めたときは、税務署に「開業届」を提出します。
個人事業から生じた所得には、所得税がかかるのですが、「開業届」は、所得の区分が、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかにあたる場合に提出することになっています。
- 事業所得・・・対価をもらって継続的に行われる事業から得られる所得
- 不動産所得・・・不動産を賃貸して得られる所得
- 山林所得・・・山林の伐採や売却から得られる所得
事業所得については、業務内容について、特に制限はありません。
ただし、事業として社会的に認められるものかどうかなどを総合的に判断することは必要になります。事業といえないもの(例:本業に比べてほんの少しの収入しかない副業など)は、雑所得で申告します。
雑所得の場合、開業届の提出義務はありません。税務署の他にも、個人事業を始めたときは、都道府県に「事業開始等申告書」などを、都道府県ごとのルールにしたがって提出します。都道府県は、個人事業税という税金を個人事業主から徴収します。
事業税の税率は、個人事業の内容が、税法で定められた第1種事業(37業種)、第2種事業(3業種)、第3種事業(30業種)のどれにあたるかで変わります。都道府県への申告書は、この税金を計算するために提出するものになります。
個人事業主が開業する為の手続きについて、こちらの記事も参照ください。
個人事業主とフリーランスとの違い
近年「フリーランス」という働き方が、注目されています。
厚生労働省のガイドラインによると、フリーランスには法令上の定義がないと前置きした上で、「フリーランスとは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指す」と、ガイドライン上の定義を示しています。
(参考)厚生労働省:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
httpss://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
このガイドライン上では、あくまで自身のスキルを基盤に収入を得る働き方をする人をいい、個人事業主だけでなく法人成りした一人社長も含むということです。
では、個人のフリーランスは、開業届の提出が必要でしょうか。
開業届の提出が必要になる場合もあれば、必要がない場合もあります。税務署への開業届は、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる事業を営む人が提出するものですから、フリーランスの所得が何にあたるかで判断することになります。「フリーランスだから」という理由で、開業届を出す・出さないを判断するわけではありません。
法人とは
法人とは、法律によって人と同様に、行為の主体となることや、権利や義務の帰属が認められる組織をいいます。
法人の分類(営利法人・非営利法人)
法人には、営利法人と非営利法人という分類があります。
営利法人とは、人や法人が出資して事業を行い、その活動から生じた利益を、出資者に分配することが認められる法人のことです。会社法上の株式会社、合同会社、合資会社、合名会社などがこれにあたります。
これに対し、営利を目的としない法人もあります。「営利を目的としない」とは、事業でお金をもらってはいけないということではなく、事業から生じた利益剰余金を出資者に分配してはいけないということです。非営利法人でも、その活動に伴い金銭を受け取って構いませんし、収益を上げることができる事業を行うことも禁じられていません。
非営利法人の代表例は、人を基礎とする一般社団法人、財産を基礎とする一般財団法人です。他にも、NPO法人(特定非営利活動法人)などがあります。
個人事業主と法人の違い
個人事業主と法人の違いについて解説いたします。
違い①設立費用
個人事業を開始する際に、必ず支払わなければならない費用は特にありません。
業種によっては許認可を受けるために行政機関に手数料を支払いますが、これは法人にも同じことがいえます。
これに対し、法人を設立する場合は、登記のための費用が必ず発生します。
株式会社を設立する場合は最低でも20万円、合同会社を設立する場合は最低でも6万円必要です。
また、定款作成や登記申請などを専門家に依頼すれば、その分の報酬も別途発生します。
違い②開業方法
個人事業を開業したときは、税務署や都道府県に届け出をします。
法人の場合は、法人設立の登記をした後に、税務署、道府県、市区町村の3箇所に法人設立届を提出します。(書類の名称は、提出先によって異なる場合があります)
東京都の場合、提出先は、税務署と都税事務所の2箇所になります。
違い③信用
一般的に、取引相手として信頼されやすいのは法人です。
登記によって基本情報がオープンにされていますし、組織で業務を行っていることが一般的ですから、安心感があります。
これに対して個人事業主は、開業するのも廃業するのも簡単ですので、「ちゃんと仕事をしてくれる人だろうか」と不安に感じる人もいます。 個人が主体ですので、その人が仕事を続けられなくなったら、それでお終いになってしまうイメージもあります。
違い④社会保険料
個人と法人では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければならない基準に違いがあります。
個人事業主は、常時5人以上の従業員が働いている場合に社会保険の適用事業所となります。
法人の場合は、社長1人でも社会保険の適用事業所となります。
このことから、2~3人しか従業員がいなくても、法人には社会保険料の負担が生じるということです。
違い⑤経費の幅
個人事業は、法人よりも経費の幅が狭くなります。
たとえば、個人事業主が売上から生活費を引き落としても一切経費になりません。
しかし、これを法人化し、役員報酬として事業から個人に金銭を支給するときは、定期同額など一定の方法で支給する限り、全額が法人の経費になります。
また、同一生計の家族に支払う給与を、個人事業で経費にするには「事業専従者」であることが前提となりますが、法人には、そうしたルールはありません。
違い⑥事業年度
個人事業主の事業年度は、カレンダーどおり1月1日から12月31日までになります。
変更することはできません。
これに対し、法人の事業年度は、任意の月から始めることができます。
決算や税務申告の時期が、事業の繁忙期と重ならないようにしましょう。
違い⑦赤字の場合
個人事業が赤字の場合、事業の所得に対して所得税や事業税などがかかることはありません。
これに対し、法人では、赤字でも法人住民税の均等割などが発生します。
法人住民税の均等割は、少なくとも毎年7万円になります。
違い⑧赤字繰り越し
所得税と法人税では、所得がマイナスになったとき、そのマイナスを翌年以降に繰り越して、翌年以降の黒字から控除することができます。
個人は翌年以降3年、法人は9年繰り越すことができます。
個人事業主のメリット
個人事業主のメリットについて解説いたします。
手続きが簡単で費用なし
個人事業を開業する際、法人のように登記の手続きはありません。
開業後に、税務署や都道府県税事務所に届け出をすれば、OKです。
費用なしで、誰でもすぐに始めることができます。
税務申告が楽
個人事業主は、所得税の確定申告を税務署に行えば、個人事業税、住民税の申告は不要になります。
個人事業税や住民税は、確定申告の内容から都道府県や市区町村が税額を計算し、後に通知されるしくみになっているからです。
所得税の確定申告の方法だけ知っていれば、個人事業の税務申告は問題ありません。
これに対し、法人は、法人税の申告を税務署に、法人事業税や都民税・道府県民税の申告を都道府県税事務所に、法人市町村民税の申告を市町村に行います。
つまり、3箇所(東京都は2箇所)に別々の税金を、法人が自ら計算して申告しなければなりません。
もちろん、それぞれの税金は、計算方法が違います。
白色申告と青色申告とは?
青色申告とは、所得税・法人税の申告方法のことで、より信頼性の高い申告方法をいいます。
青色申告を始めるには、税務署に、「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
承認を受けた上で、青色申告の要件を満たす確定申告を行うと、節税に有利なさまざまな特典が受けられます。
所得税の主な特典は、下記のとおりです。
- 青色申告特別控除65万円(55万円)・10万円
- 青色事業専従者給与の必要経費算入
- 3年間の純損失の繰越控除
など
白色申告とは、青色申告でない申告方法のことです。
一定の利益までは個人事業主が得
個人の事業にかかる税金には、所得税、個人事業税、住民税があります。
所得税の税率は、5%~45%で、所得の高い部分ほど、高い税率が適用されます。
個人事業税は3%・4%・5%のいずれかです。
住民税は、所得の10%の所得割と5,000円ほどの均等割の合計となります。
これらを合算すると、個人の場合、事業の所得に対して20%~60%くらいの税負担になることがわかります。
法人は、法人税、地方法人税、法人事業税、特別法人事業税、法人都民税(法人道府県民税・法人市町村民税)と、税金の種類が多く、計算も複雑なのですが、これらの税金をまとめ、所得に対して大体どのくらいの負担になるかを計算した「実効税率」というものがあります。
法人税等の実効税率は、法人の規模や所得などで変わりますが、25%~35%くらいです。
したがって、事業の所得が低い間は、個人のほうが税負担を抑えることができます。
個人事業主のデメリット
続いては個人事業主のデメリットについて解説いたします。
社会的信用度が低い
個人事業主は、法人のように登記の必要がなく、誰でも簡単に始めることができます。
コストもかからないため、小遣い感覚で始める人も少なくありません。
また、個人事業主は一人で業務をしていることも多いので、病気やケガ、個人的な事情によって長期休業するリスクがあります。
そのため、法人と比べて、個人事業は不安定というイメージをもっている人もいます。
実績を積んで、少しずつお客さんを増やす辛抱強さが必要です。
なお、個人か法人かの違いが信用度に影響するかどうかは、業種にもよるところがあります。
たとえば、歯医者さんを探すとき、腕がいいかどうかの口コミは参考にしても、医療法人でなければ治療を受けたくないから、まず法人かどうかを調べるという人はいません。
美容院などもそうだと思います。
法人だから信頼できるという感覚が世間にはない業種があるので、ケースバイケースだということも知っておきましょう。
人材採用で不利
まったく同じ条件で、個人と法人の求人があったとしても、法人は、個人事業よりも安定して働けるイメージがありますので、採用面でも、法人より不利になりやすいといえます。
ただし、働き手のニーズも多様化していますので、たとえば、法人にはできないフレキシブルな働き方を認めるなど工夫すれば、能力は高いのに、時間や場所、子育てなどの制約によって働き口が見つからない人材を発掘できる可能性があります。
必要な人材があれば、求人票を出し、粘り強く待ってみましょう。
利益が多くなると税金が多くなる
メリットの裏返しとなりますが、個人事業は、利益が増えると法人よりも税負担が重くなります。
理由は、所得税の税率の上昇幅がとても大きいからです。
| 課税所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上~330万円未満 | 10% |
| 330万円以上~695万円未満 | 20% |
| 695万円以上~900万円未満 | 23% |
| 900万円以上~1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上~4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
課税所得金額とは、事業の所得から、青色申告特別控除や所得控除(社会保険料控除や基礎控除など)を差し引いた後の金額です。
計算例を見てみましょう。
たとえば、課税所得金額が300万円のとき、税率は、195万円までの部分は5%(195万円×5%=9万7,500円①)で、195万円以上300万円までの105万円分(105万円×10%=10万5,000円②)の部分は10%になります。
したがって、300万円に対する所得税額は、20万2,500円(①+②)で、所得に対する負担率は6.75%です。
これが1,000万円になると、所得税は176万4,000円で、負担率はいっきに17.64%まで上がります。
これに個人事業税、住民税の税率が加わりますので、課税所得金額1,000万円にもなると、所得に対してかなりの税金がかかることがわかります。 個人事業は法人と比べて経費にできるものが少ないため、利益が増えてきたら法人化を検討しましょう。
個人事業主や法人の税金について、ご不明点等ございましたら弊所へご連絡ください。
法人のメリット
続いては法人のメリットについて解説いたします。
社会的信用度が高い
法人は、その運営などに関するルールが会社法などで定められています。
事業を始めることも難しいのですが、事業を辞めることも簡単ではありません。
また、取締役の住所・氏名をはじめとする会社の基本情報については、登記事項を見ることで、誰でも確認することができますし、株式会社には決算公告の義務もありますので、個人事業よりも経営内容がオープンになっています。
こうした違いから、法人は個人よりも信頼されやすく、取引や採用面で有利に働くといえます。
節税面でのメリットが大きい
事業の所得が増えてくると、法人化したほうが、個人よりも税負担が軽くなります。
このことは「個人事業主のデメリット」でお伝えしたとおり、所得税の税率の累進性がびっくりするほど大きいからです。
| 課税所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上~330万円未満 | 10% |
| 330万円以上~695万円未満 | 20% |
| 695万円以上~900万円未満 | 23% |
| 900万円以上~1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上~4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
では、法人税はどうなのかといいますと、法人にかかる税金にも、超過累進税率を適用しているものがあります。
| 課税所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 年800万円以下 | 15% |
| 年800万円超 | 23.20% |
| 課税所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 年400万円以下 | 3.5% |
| 年400万円超年800万円以下 | 5.3% |
| 年800万円超 | 7.0% |
ご覧のとおり、法人の税金に適用されている累進税率は、個人に比べて上昇幅が緩やかになります。
個人や法人にかかる税金は、所得税、法人税、法人事業税以外にもありますが、他を含めても、所得が大きくなるほど節税に有利なのは法人です。
なお、法人と一口にいっても、会社の規模で税金のかかり方が異なります。
法人には、資本金の額、事業所の数、従業員数などで増える税金があるからです。
小規模で所得が低い会社ほど、税負担が低くなります。
資金調達が個人事業主よりしやすい
事業の規模が大きいほど、大きな資金調達がしやすくなります。
そういった意味では、資金調達の面でも法人が有利です。
また、法人には、会社法で債権者保護に関するルールもきちんと決められていますので、金融機関からすれば、個人に貸すよりも安心できる部分があるといえるでしょう。
また、株式や社債の発行といった、個人ではできない資金調達手段も認められています。
なお、事業内容が魅力的であれば、クラウドファンディングもおすすめの資金調達方法です。
これについても、社会的信用度の高さから、法人であることが有利に働くことが考えられます。
法人のデメリット
続いては法人のデメリットについて解説いたします。
会社設立に時間が掛かる
定款作成、資本金の払込み、登記申請など、設立まで設立までの道のりが長いことが、法人のデメリットです。
一般的に、1~2か月くらいの準備期間が必要になります。
会社設立に費用が掛かる
法人は、設立するだけで費用がかかります。
株式会社設立での費用
- 定款の認証 5万円
- 定款の印紙税 4万円
- 登録免許税 最低15万円
合同会社設立での費用
- 定款の印紙税 4万円
- 登録免許税 最低6万円
定款の印紙税は、電子定款にすることでカットできますので、最低でも株式会社で20万円、合同会社で6万円必要です。 そして、設立後も、役員の変更登記、株式会社の決算公告費用など、法人ならではの運営コストが発生します。
赤字でも税金がある
赤字でも税金があるため注意が必要です。
消費税
消費税の簡易課税を選択している場合、課税売上高から計算した消費税額に一定の割合をかけて仕入控除税額を計算します。
たとえば、課税売上高1,100万円(うち消費税額100万円)のとき、小売業であれば80%の仕入率で仕入控除税額を計算するため、80万円を控除した残り20万円を税務署に納税することになります。
このことから、課税売上高があれば、たとえ事業が赤字でも消費税の納税額が生じるので注意が必要です。
一般課税の場合であっても、課税仕入れがなければ、赤字でも納税額が生じる可能性はあります。
なお、消費税は、課税事業者の要件を満たせば、個人にも納税義務があるため、法人のみのデメリットとはいえないかも知れません。
しかし、申告件数や納税額は、個人よりも法人のほうが多いため、赤字でも納税が必要なケースがあることについて、より注意が必要なのも法人といえるでしょう。
法人住民税の均等割
法人が申告する法人住民税(都民税)は、法人税割と均等割の2つ税額の合計となります。
このうち均等割は、法人の事務所や事業所があるだけで発生するため、赤字でも最低7万円の納税額が発生します。
均等割の額は、資本金の額と従業員の数で決まります。
一部法人の法人事業税
法人事業税は、法人の所得をもとに計算されますが、主に下記の事業では、所得ではなく収入をベースに法人事業税を計算します。
- 電気供給業(小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業を除く)
- ガス供給業
- 保険業
たとえば、保険業では、収入保険料に付加保険料率をかけた金額に対して、法人事業税がかかります。
この方法では、赤字になったとしても、税負担が生じます。
上記の事業は、所得に対して課税すると、法人の活動量と税額が合わなくなってしまうという理由から、このような課税方法になっています。
社会保険の加入が必須
社会保険の加入が必須になるため注意が必要となるので解説いたします。
社長一人でも社会保険加入が義務
たとえ社長一人しかいなくても、法人は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しなければなりません。
厚生年金に加入できることはデメリットではないという見方もできますが、法人の負担はその分大きくなります。
従業員の社会保険料負担分がある
社会保険に加入すると、その対象者の保険料の半分を、事業者が負担しなければなりません。
たとえば、協会けんぽの健康保険料は、対象者が40歳未満であれば、その人の標準報酬月額の9.84%、40歳から11.64%になります。(※)
厚生年金保険料は、標準報酬月額の18.3%です。
これらの半分を、毎月法人で負担しなければなりません。
(個人事業主でも社会保険が適用される事業所では、事業主が保険料を半分負担しなければなりません。)
(※)保険料率は、令和3年3月分以降の東京都の料率になります。
httpss://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30213tokyo.pdf
まとめ
個人事業主、法人のメリット・デメリットについてまとめると以下の通りです。
- 個人事業主のメリットは税務申告が楽、一定の利益までは個人事業主が有利
- 法人のメリットは所得が大きくなると節税になる、資金調達がしやすく、社会的信用度が高い
- 個人事業主のデメリットは社会的信用度が低く、採用が難しい、利益が大きくなると税金が大きくなる。
- 法人のデメリットは会社設立に時間・費用がかかる、赤字でも税金がかかる、社会保険に入る事が義務であるため、負担しなければならない。

いかがでしたでしょうか?
個人事業主と法人の違いについて解説してきました。
個人事業主、法人ともにメリット・デメリットがあるため、どちらが自分にとって有利なのかしっかりと確認して行きましょう。
不明点は税理士にすぐに確認しましょう。
【こちらもおすすめ】
ネットショップを一人で運営するには|開業方法から成功ポイントまで徹底解説 – OPENLOGI オープンロジ
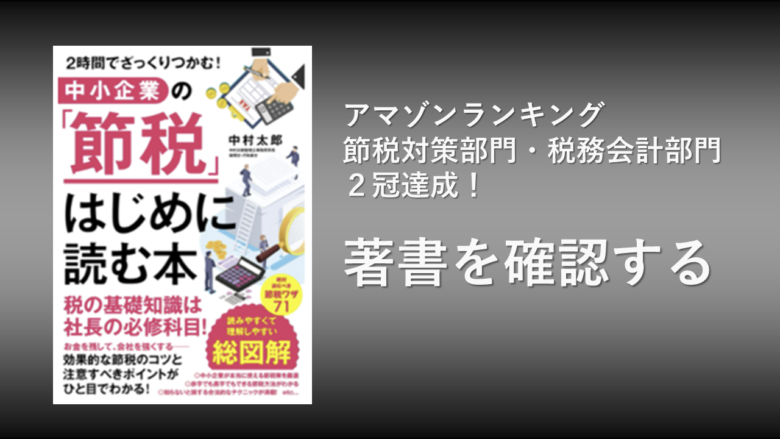









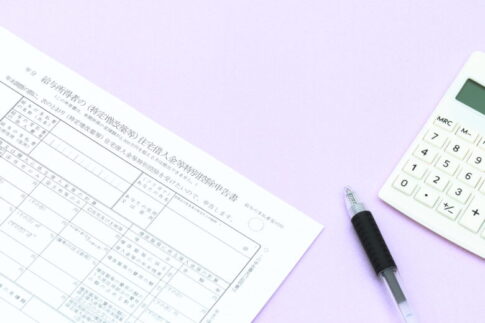




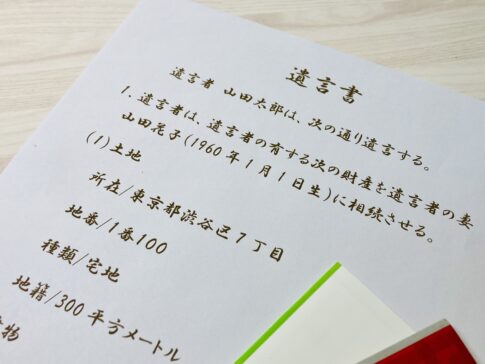




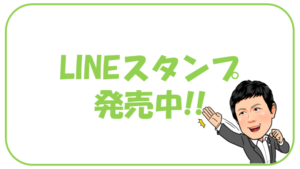
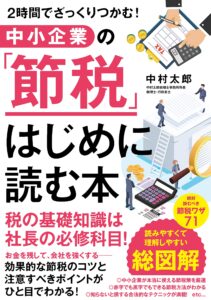

まいど!西新宿の税理士 中村です!
個人事業主と法人どちらのほうが税金上有利になるのかについてご存じでしょうか。
この記事では、個人事業主と法人の違い、それぞれのメリット、デメリットについて解説いたします。