中小企業において節税対策が重要な理由
中小企業が支払う税金が多岐にわたるため
中小企業には、法人税や法人事業税、法人住民税、消費税など、多くの税金がかかります。
中には、所得のない事業年度においても発生する、住民税の均等割のような税金もあります。
ほかにも、登記の度にかかる登録免許税、一定の文書を作成する度にかかる印紙税などがあります。
このように、中小企業が支払う税金は多岐にわたるため、節税しなければ会社のお金がどんどん減ってしまいます。
毎年安定した利益が出るとは限らないため
中小企業の経営環境は、日々変化します。
強力なライバル企業の出現、消費動向の変化、法制度の改正、災害発生や感染症の流行といったさまざまな要因による利益減少に備えなければなりません。
中小企業の節税は、こうした有事の運転資金等を確保する方法としても重要です。
法人税及び復興特別法人税
法人税
法人税は、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。
法人の所得金額は、益金の額から損金の額を引いた金額となっています。
税務上の利益(課税所得) = 益金 - 損金
上記の課税所得と法人税率を用いて法人税を計算します。
法人税 = 課税所得×法人税率-控除額
<普通法人の場合の税率>
| 所得金額 | 税率 | |
|---|---|---|
| 資本金1億円以下の法人など | 年800万以下 | 15.0% |
| 年800万円超 | 23.2% | |
| 上記以外の普通法人 | - | 23.2% |
法人税は、個人の所得に対してかかる「所得税」に相当する税金です。
最も大きな違いは、「税率」です。
所得税は所得が高くなればなるほど税率は高くなる累進課税制度をとっていますが、法人税は本金・法人の種類によって異なるものの、税率は一定です。
法人住民税
法人住民税とは、都道府県または市町村に事務所や事業所などがある法人に課される税金です。個人に課税される住民税と区別するために「法人住民税」と呼ばれます。
道府県民税と市町村民税があり、これらを合わせて法人住民税と呼びます。
法人住民税には、それぞれ均等割と法人税割があります。
均等割は所得が赤字か黒字かに関係なく、資本金・従業員数に応じて課税されます。
法人税割は法人税額をもとに算出されます。
| 法人 住民税 | 道府県民税 | 均等割 | 資本金・従業員数などに応じて課税される | ||
| 法人税割 | 法人税額を基礎として課税される | ||||
| 市町村民税 | 均等割 | 資本金・従業員数などに応じて課税される | |||
| 法人税割 | 法人税額を基礎として課税される | ||||
法人住民税は、地方公共団体によって税額、税率が変わりますので、不明点等は税理士に相談することをおすすめします。
法人事業税
法人事業税は、法人が事業を行うために利用する公共サービス・公共施設の経費を、地方公共団体に対して一部負担する目的で課税されます。
法人事業税額 = 所得×法人事業税率
法人税が国に対しての税であるの対して、法人事業税は都道府県に対して支払う税金です。
法人事業税は、黒字の会社に対してかかりますが、所得の大きさにより段階的に税率が変わります。
算出後、法人住民税とともに申告します。
法人事業税率は、下記の条件によって異なります。
- 法人の種類
- 課税所得
- 事業開始年度
また、各都道府県によっても税率は異なるため、地方自治体のホームページで事前に確認したり、不明点などは税理士に相談しておきましょう。

消費税
法人は、売上で受け取った消費税から、仕入れ先などに支払った消費税を差し引いた残りを計算して納税します。
消費税は、基準期間(法人では原則として前々事業年度)における課税事業年度の課税売上高に対して課されることになっています。
設立したばかりで基準期間がない法人については、資本金または出資の金額が1,000万円未満であれば、免税事業者になります。
消費税についてはこちらの記事でも詳しく解説しておりますのでぜひご覧ください。
印紙税
印紙税は、契約等に伴って契約書や領収書、約束手形などの文書を作成した場合に、その文書に課税される税金です。
5万円以上の領収書など課税文書を作成したときにかかる税金で、収入印紙を貼って消印を押すことで納税になります。
登録免許税
登録免許税は、法人に関する商業登記や不動産登記を行う時に納める国税です。
登記手続きは、土地や建物の引き渡しと同時に行われるのが原則です。
税額が3万円以下の場合は印紙納付をすることもできます。
固定資産税
固定資産を保有していることで課税される地方税です。
課税対象となる財産には次のものがあります。
- 土地
- 建物
- 一定金額以上の償却資産
自動車関連の税金
2019年に税制が大きく改定され、現在、車に関する税金は以下の4種類になっています。
- 自動車税 / 軽自動車税
- 自動車重量税
- 環境性能割
- 消費税
中小企業におすすめの節税対策
次に、中小企業におすすめの節税対策を9つご紹介します!
法人保険への加入
保険金を簿外資産として準備することが可能です。
たとえば、養老保険では、役員や従業員を被保険者とし、死亡保険金の受取人を「被保険者の遺族」、満期保険金(満了時に生存している場合に支払われる保険金)の受取人を「法人」とすることで、保険料の2分の1を経費にすることができます。
定期保険には、支払った保険料の全額を損金にできる法人保険もありますが、令和元年7月8日以降契約分では、全額を損金にできる保険商品の範囲がかなり狭くなっています。
設備投資を行う
青色申告法人である中小企業は、「中小企業経営強化税制」などを活用することで、節税しながら設備投資をすることができます。
下記のいずれかの選択
- 即時償却
- 7%または10%の税額控除(法人税の20%相当額まで)
中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定を受けて行う、特定経営力向上設備等の取得が対象です。
(参考)国税庁:中小企業経営強化税
httpss://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm
節税効果はやや下がりますが、認定の要らない「投資促進税制」もあります。
(参考)国税庁:中小企業投資促進税制
httpss://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
少額減価償却資産を取得する
決算が近くなり、「もう少し節税したい」という場合は、少額減価償却資産の取得がおすすめです。
取得価額が10万円未満である資産は、その全額は経費にできます。
さらに青色申告法人であれば、30万円未満の資産も、特例に適用することによって全額を経費にすることができます。
中古資産を購入する
中古資産の場合、通常よりも短い耐用年数で減価償却ができるため、節税に有効です。
たとえば中古車は、定率法であれば、普通車は4年落ち、軽自動車は2年落ちで、1年で経費にすることもできます。
ただし、減価償却費は、新品の資産と同じで、事業に使用した期間における月割り計算をしなければなりません。
したがって、事業年度の途中から使用する場合、全額を経費にできないためご注意ください。
固定資産の見直しを行う
すでに廃棄した資産や、古い事業に使っていて二度と使用する見込みのない資産が、帳簿の上ではまだ整理されていない場合があります。
これらは、帳簿の残額を除却損として計上できる場合がありますので、確認しましょう。
人材投資を行う
前年度よりも給与をアップした場合、賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制。令和4年4月1日以降の事業年度から適用開始)の要件に該当すれば、さらに節税できる可能性があります。
- 雇用者給与等支給額+1.5%以上
→15%の税額控除
- 雇用者給与等支給額+2.5%以上
→30%の税額控除
- 教育訓練費+10%以上
→上記の税額控除に10%を上乗せ
税額控除は法人税の20%が上限になります。
出張手当を支給する
出張の機会が多い会社であれば、実費よりもやや多めの「日当」を支給することで、節税することもできます。
「日当」は、社内の出張旅費規程などに従って支給すれば、個人の給与課税の対象にならず、国内出張であれば消費税の仕入税額控除にもなるため、実費精算における税務のメリットもそのままです。
さらに、従業員にとっては精算しづらい出張先での諸々の自己負担が減少し、経理担当者にとっては精算額がわかりやすくなるといったメリットがあります。
社員旅行などの福利厚生を充実させる
福利厚生のための費用も、基本的に全額が経費となりますので、節税効果があります。
たとえば、社員旅行を実施したり、社宅やスポーツジム、託児所などを借り上げたりすることが考えられます。
従業員の士気が高まるもの、定着率の上がるもの、採用活動においてPRになるものなどを選択するとよいでしょう。
過度に豪華なもの、特定の人物しか利用できないもの、金銭受給との選択が可能なものなどは、月分給与として給与課税の対象になります。
設立時の資本金を1,000万円未満とする
法人の設立時、資本金や出資金の額を1,000万円以上にすると、初年度から消費税の課税事業者になってしまいます。
よって、設立時の資本金等の額は、1,000万円未満としたほうが節税に有利です。
1,000万円未満でも、初年度から課税事業者になる例外があります。
まとめ
中小企業は、資金に余裕があるときこそ確実に節税し、その分を、将来のために企業に残すことが大切です。
特に、人材や設備投資のように、従業員や顧客に還元できる節税方法が、企業の成長にもなる効果的な節税といえるでしょう。

いかがでしたでしょうか。
冒頭でも申し上げた通り、きちんと節税することが会社経営において重要となります。
節税の必要性、効果的な節税方法を知ることが節税の第一歩となります。
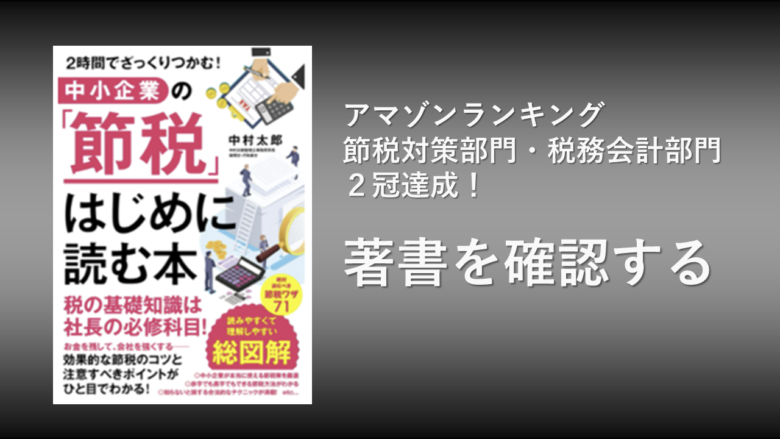










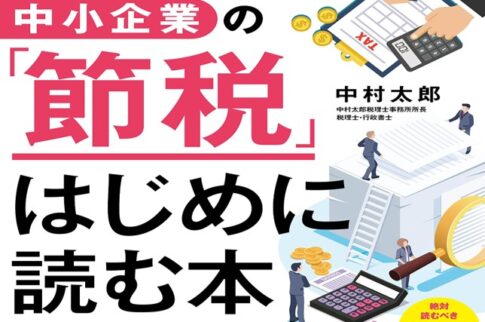





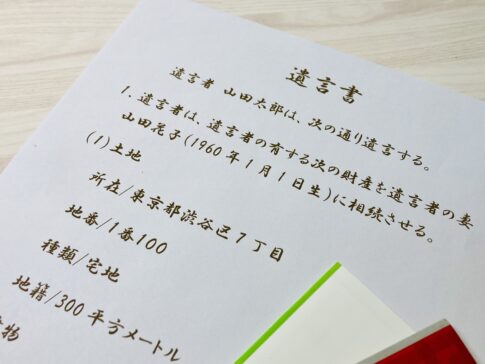

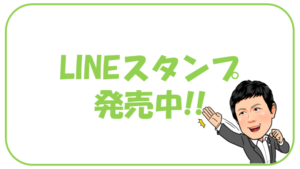
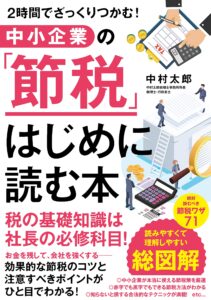

まいど!西新宿の税理士 中村です!
今回は、【中小企業が知っておくべき節税対策】をテーマに解説致します。
節税は私が得意とする分野、是非ご一読ください!