期限後申告とは
「期限後申告」とは、申告期限を過ぎてから行われる確定申告などのことです。
期限までに申告書を提出した確定申告を「期限内申告」、期限を過ぎてから申告書を提出した確定申告を「期限後申告」として区別します。
たとえば、所得税の確定申告の申告期限は、申告対象年の翌年の3月15日ですから、この場合、3月15日までの申告が「期限内申告」に、3月16日以降の申告が「期限後申告」になります。
もしも提出した確定申告書が「期限後申告」にあたる場合、その確定申告は、通常よりも不利な扱いを受けます。
確定申告を忘れた場合、いつまで期限後申告を受け付けてくれるのか?
税務署がいつまで期限後申告を受け付けるのかというと、その申告期限から5年間です。
法律で提出期限を直接定めているわけではなく、国税の徴収権の時効が5年であることから、5年を過ぎた期限後申告は基本的に受け取らないことになっています。
ただし、納税者に隠ぺい工作などの不正があると、この5年が7年になります。
そのため、税務調査で不正が発覚したことによって、期限後申告の提出を過去7年までさかのぼって求められることがあります。
状況によっては無申告加算税や重加算税などがかかることなく期限後申告できる可能性があります。
税務調査が入る前にできる限り早く期限後申告を済ませることをおすすめします。
中村太郎税理士事務所では期限後申告の対応も受け付けております。
お気軽にご相談ください。
期限後申告をするメリット
無申告のペナルティやリスクを低減できる
確定申告期限を過ぎてから期限後申告をするまでの間は、「無申告」の状態です。
この間に税務調査が行われ、確定申告をしなければならない所得があったことが発覚すると、本来の税額にプラスしてペナルティの税金が発生します。
ただし、税務署から連絡を受ける前に、自発的に期限後申告をすることによって、このペナルティを最小限に抑えることができます。
詳しくは、後述する「期限後申告のペナルティ」をご覧ください。
払い過ぎた税金が戻ってくることがある
期限後申告をすることで、税金が戻ってくるケースもあります。
期限後申告が”還付申告”にあたる場合がある
給与やボーナス、報酬、年金などから源泉徴収された所得税がある人のうち、その年に本来納税すべき所得税が給与等から徴収された税額よりも少ない人は、確定申告をすることによって、差額の還付を受けることができます。
還付を受けることができる期間は、申告対象年の翌年1月1日から5年間ですので、もちろん期限後申告になっても構いません。
次のようなケースにあてはまる方は、期限後申告をすると税金が戻ってくる可能性がありますので、過去5年間でそういった年がなかったかどうかをチェックしてみてください。
会社員
- 医療費控除など、年末調整で適用していない控除がある
- 副業で不動産投資をしており、赤字の年がある
個人事業主・フリーランス
- 予定納税をしているが、前年よりも業績が悪かった
- 受け取った報酬から源泉徴収されている
その他
- 公的年金、保険会社の個人年金などから源泉徴収されている
控除しきれない損失がある場合も期限後申告
事業所得や不動産所得などに損失が生じ、損益通算をしても控除しきれないマイナスが残る場合、確定申告(青色申告)をすることで、その損失を翌年以降に繰り越して控除することができます。
ある年に発生したマイナスを将来(最大3年)にわたって繰り越し、繰り越した年の黒字と相殺することによって、相殺した年の税負担を軽減できるのです。
この場合に行われる確定申告は、期限後申告でもかまいません。
また、株式や先物・オプション取引など分離課税の各所得でマイナスが生じた場合も、確定申告をすることによって損失を繰り越すことができます。
ただし、損失の繰越控除の確定申告をし、その後に、連続して(黒字の年分などの)確定申告書を提出することが条件となります。
無申告加算税が軽減される
期限後申告をすると、その申告税額に対し、15%(50万円を超える部分に対しては20%)の「無申告加算税」が課されます。
ただし、税務署からの通知を受けることなく自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。
期限後申告を行うことで上記のようなメリットがあります。
忙しくて申告期限に間に合わなかったという方は、できるだけ早く期限後申告して、無申告加算税の軽減や日割りでかかる延滞税を軽減しましょう。
中村太郎税理士事務所では期限後申告の対応も受け付けております。お気軽にご相談ください。
期限後申告のペナルティ
無申告加算税
無申告加算税とは、期限後申告や期限後申告に対する修正申告をしたとき、その申告で納めるべき税額に対して発生するペナルティの税金です。
基本的には、その申告で納めるべき税額の15%(50万円を超える部分に対しては20%)ですが、税務署からの調査の通知を受ける前に期限後申告を行うことで軽減されます。
具体的には、次のとおりです。
【無申告加算税の税率】
| 期限後申告をする時期 | 無申告加算税の税率 |
| ~調査通知前まで | 5% |
| 調査通知後 ~更生又は決定の予知前 | 10% (15%) |
| 更生又は決定の予知後 | 15% (20%) |
延滞税
延滞税とは、無申告や過少申告などによって、本来、法定納期限(基本的には申告期限と同じ日)までに納めるべき税額が支払われていない場合、その未納の税額に対して発生するペナルティの税金です。
延滞税の金額は、未納税額と、法定納期限から遅れた日数によって計算されるため、納税が遅れるほど高くなります。
延滞税の税率は、2つあります。
1つは、法定納期限を過ぎた直後の日数にかかる税率で、もう1つは、納期限(※)から2か月を過ぎた日数に対してかかる税率です。
税率は、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、毎年見直されます。
参考までに令和4年中の延滞税の税率は、法定納期限後が年2.4%、納期限から2か月経過後が年8.7%でした。
(※)期限後申告では、期限後申告の提出日が納期限となります。
控除が無効になる
期限後申告では、一部の有利な税制が使えなくなってしまいます。
代表的なものは、青色申告特別控除(55万円または65万円)です。
青色申告特別控除(55万円または65万円)とは、事業所得や不動産所得の確定申告をする個人事業主が、一定の要件を満たすことで適用できる控除です。
必要経費を引いた後の金額から、さらに55万円(最大65万円)を差し引くことができるため、かなり高い節税効果を得ることができます。
しかし、適用するには確定申告(青色申告)を期限内に実施することが必要となりますので、期限後申告では受けられません。
なお、青色申告特別控除(10万円)であれば、期限後申告であっても受けることができます。
期限後申告をする場合の注意点やポイント
忙しくて申告期限に間に合わなかった場合はできるだけ早く期限後申告を!
期限後申告によって発生する無申告加算税や延滞税は、1日でも早く自発的に期限後申告をすることで軽減されます。
そのため、確定申告の期限に間に合わなかったとしても、できるだけ早く期限後申告を行うことがポイントです。
特に遅れてまだ1か月も経っていないのであれば、無申告加算税については、次の2つの条件を満たすことで不適用となります。
- その期限後申告が、法定申告期限が1か月以内に自主的に行われていること
- 期限内申告をする意思があったと認められる「一定の場合」に該当すること
「一定の場合」とは、次の両方に該当する場合をいいます。
- その期限後申告による納税額をすべて法定納期限(口座振替は期限後申告をした日)までに納付していること
- その期限後申告書を提出した日の過去5年内に、無申告加算税または重加算税をかされたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められたことによって無申告加算税の不適用を受けていないこと
過去の損失を申告していなかった場合は申告漏れがなかったかチェック!
期限後申告をすることで、払い過ぎていた税金が戻ってくる場合もあります。
税金を還付してもらうための確定申告は5年までさかのぼってできますので、該当する年がないかチェックしてみましょう。
また、損失がある場合は、その損失を翌年以降に繰り越して控除することもできます。
個人事業や副業で赤字になった年がある方、株やFX投資などの損失がある方などは、この機会にチェックしてみましょう。
前述の「払い過ぎた税金が戻ってくることがある」の内容もご参考にしてください。
無申告状態が長期間続いている場合は税務調査の対象としてリストアップされている可能性が!
確定申告をずっとしていない方の中には、税務署から特に連絡がないため意外と大丈夫なんだと考えている方もいるかも知れません。
しかし、税務署からの連絡は、2年後や3年後になることもあります。
実はすでに税務調査の対象としてリストアップされており、ある日突然、数年分の所得に対してまとめて税務調査が入って、さかのぼれる年分まで税金を徴収されてしまう可能性もあります。
期限後申告のやり方
期限後申告のやり方は、通常の確定申告と同じです。
期限後申告だからといって、特別な方法や用紙があるわけではありません。
損失の繰越控除などを適用する際に、確定申告書に添付しなければならない書類についても、通常の確定申告と同様です。
まとめ
期限後申告がいつまでできるのか、期限後申告を自主的に行うことのメリットや、期限後申告のペナルティについて解説しました。
確定申告を忘れてしまった際の期限後申告は、なるべく早く自分からすることが大切です。
しかし、慌てて確定申告書を作成したせいで、期限後申告の内容に誤りが見つかり、それが申告税額の不足であると再び修正申告をして追加の加算税等を支払うことになってしまいます。
期限後申告をするときは、税理士に依頼し、確実な確定申告書を提出することをおすすめします。

いかがでしたか?
期限後申告には厳しいペナルティがございます。なるべく早く、自分から申告・納税することが一番大切です。
何かしらの事情で期限内に申告が出来なかった場合には、どうせ遅くなったからと後回しにせず、出来る限り早く対応しましょう。









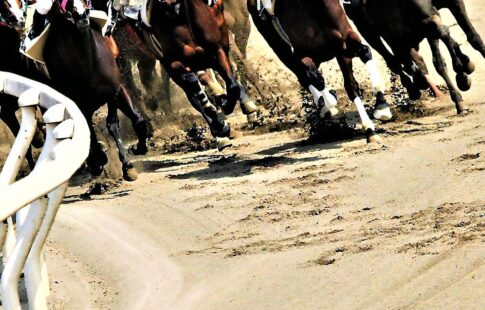

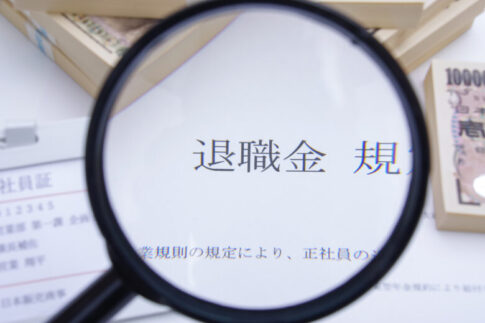





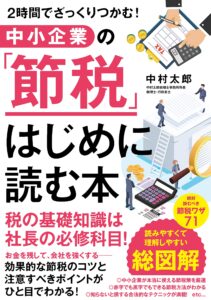

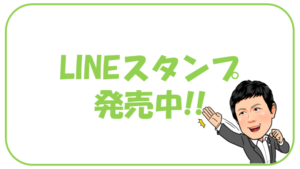
まいど!西新宿の税理士 中村です!
今回は【期限後申告】について。
毎年3月15日が確定申告の期限となっておりますが、事情があり期限に間に合わない方もいらっしゃるかと思います。
本記事では申告期限を過ぎての確定申告の仕方を解説いたします。
是非ご一読ください!