社宅とは
社宅とは、会社が役員や従業員のために用意する住まいのことです。
福利厚生の向上により、人材の採用や定着に有利に働きます。
さらに、社宅のために支払ったお金は経費になり、会社の節税にもつながります。
社宅の種類
まずは、社宅の種類を見ていきます。
社宅には、会社で社宅用の物件を購入したり建築したりして所有する「自社所有の社宅」と、賃貸物件を会社で借り上げて会社から従業員に転貸する「借り上げ社宅」があります。
どちらの社宅でも節税は可能です。
自社所有の社宅
自社所有の社宅とは、会社が購入した物件や新築した物件のように、会社名義で所有するタイプの社宅です。
従業員を入居させる際は、会社と従業員の間で建物賃貸借契約を締結します。
会社が貸し手であるため、入居や退去の手続きをスムーズに進めやすいなどのメリットがあります。
ただし、この方法を取る場合は会社側の支出が大きくなります。
物件を取得する費用がかかる上、その後も管理料(清掃費や修繕費、固定資産税をはじめとする税金など)が継続して発生します。
借り上げ社宅
借り上げ社宅とは、会社名義で賃貸物件を借り、従業員にそれを転貸するタイプの社宅です。
建物の貸し手は第三者である外部のオーナーとなります。
初期費用や毎月の家賃といった諸費用は、一般的には会社から管理会社に支払います。
また、会社が社宅として選んだものだけでなく、従業員が選んだ賃貸物件について会社が契約を行うスタイルでも運用できます。
なお、あくまで賃貸契約を結ぶのは会社でなければなりません。
役員や従業員が自ら契約して借りた物件の支払いを会社がするケースは対象外となるため注意が必要です。
社宅の節税で経費となる具体的な支出とは
会社が社宅のために支払う費用は、会社の経費となり法人税の節税につながります。
以下は、会社が社宅を導入した際に経費となる主な支出の例です。
【自社所有の社宅】
・仲介手数料(建物の取得価額に含めて減価償却費)
・不動産取得税、登録免許税
・固定資産税、都市計画税
・建物本体の減価償却費
・火災保険料、地震保険料
・借入金の利子
・修繕費、維持管理費用
など
【借り上げ社宅】
・契約時の費用(仲介手数料・礼金など)
・家賃、共益費、管理費など
・保証会社に支払う保証料
・火災保険料
など
従業員の社宅で節税する方法
会社が社宅のために支払うさまざまな費用は、会社の経費となり法人税の節税につながります。
その一方で、福利厚生とはいえ無対策で行うと、従業員は会社から「現物給与」を受けたものとして「従業員個人」の給与課税が必要になります。
給与課税の対象になると、月給からの源泉徴収が必要になり、年末調整でも給与の総支給額に含めなければなりません。
従業員本人の税負担が増えることも問題ですが、それ以上に、会社の税務ミスが起こらないかどうかが気になります。
できることなら、現物給与という余計な心配をせずに会社の経費にしたいところです。
そのためには、従業員から毎月「賃貸料相当額の50%以上」を徴収する方法があります。
これを行えば、社宅の費用をスムーズに会社の経費にすることができます。
従業員に給与課税が起こる理由
従業員個人に給与課税が必要となる理由は、「住まい」という経済的な利益を会社が与えることが、従業員個人への「現物給与」にあたるからです。
現物給与にあたる場合、金銭として支払っている給与と同じ扱いになります。
一体いくらの給与として扱われるのかというと、社宅の物件に応じた「賃貸料相当額」です。
この「賃貸料相当額」については後ほど詳しく解説しますが、この金額分の給与を、会社が毎月支払っているとみなされます。
それにより、源泉徴収が必要になるほか、年末調整では年間の給与の総支給額に含めなければなりません。
源泉徴収や年末調整のミスは、不納付加算税などのペナルティにつながるため、会社としては現物給与の扱いはできるなら避けたいところです。
賃貸料相当額の50%以上で給与課税なしで経費にできる
ここまでのとおり、福利厚生として会社側の経費となるものでも、それを受けた個人側では給与として課税の対象となります。
ただし、社宅のように社会的に広く認められた一般的な福利厚生のすべてに課税することは国としても好ましくありません。
そこで国税庁は、福利厚生の内容に応じてそれぞれ限度を定め、その範囲内であれば課税しなくて良いというルールを示しています。
それにより社宅の場合は、従業員が家賃の一部として「賃貸料相当額の50%以上」を会社に支払っていれば、給与として課税する必要はないとされています。
したがって、給与課税なしで社宅を経費にするには、「賃貸料相当額の50%以上」を正しく計算し、給与から天引きするなどして確実に徴収することがポイントです。
賃貸料相当額の計算方法
それでは、「賃貸料相当額」の具体的な計算方法を見ていきましょう。
賃貸料相当額は、次の1~3の合計額となります。
1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
2.12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
3.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
社宅を従業員に貸与するときは、この合計額を計算し、その50%以上を従業員から徴収するようにします。
なお、自社所有の社宅でも借り上げ社宅でも、「賃貸料相当額」の計算方法は同じです。
「賃貸料相当額」の相場
「従業員からお金を徴収するなら、あまり福利厚生として価値を感じてもらえないのでは…」という心配があると思います。
しかし、この「賃貸料相当額」は非常に少額であり、「賃貸料相当額×50%」ともなれば、同じ条件での家賃相場のおおむね2割程度になります。
仮に家賃5万円の賃貸物件を社宅とし、「賃貸料相当額×50%」が1万円だとすれば、従業員は毎月1万円を給与から天引きされるだけで、5万円相当の物件で生活できることになります。
このように「賃貸料相当額×50%」を徴収しても、福利厚生としては十分魅力的なのです。
固定資産税の課税標準額の調べ方
固定資産税の課税標準額は、以下のような書類に記載されています。
・固定資産税の課税明細書
・公課証明書
など
固定資産税の課税明細書は、建物の所有者宛てに市区町村から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に同封されています。
自社所有の社宅であれば会社宛てに毎年届くため、すぐに確認することができます。
借り上げ社宅の場合は、有料ですが借り主として市区町村に公課証明書の交付を申請できます。また、不動産管理会社に尋ねれば教えてもらえる場合もあるでしょう。
建物の総床面積の調べ方
建物の総床面積は、以下のような書類に記載されています。
・固定資産税の課税明細書
・評価証明書、公課証明書
・登記事項証明書
・建物賃貸借契約書
など
自社所有の社宅の場合は、固定資産税の課税明細書で確認することができます。
借り上げ社宅についても賃貸契約書に記載されているため、確認しやすい項目です。
賃貸料相当額を計算する時の注意点
賃貸料相当額の計算や徴収後の経理については、一度税理士に相談しておくことをおすすめします。
もしご自身で計算する場合は、以下の点に注意してください。
従業員からの徴収額は会社の収入になる
家賃の一部を従業員から徴収した場合、その徴収額は給与と相殺することなく、会社の収入として計上します。
そのため会社の経費になる家賃は、最終的には会社が支払った分と従業員から徴収した分との差額になります。
「賃貸料相当額×50%」未満の額を徴収した場合
無償(0円)ではないものの、「賃貸料相当額×50%」に届かない金額を従業員から徴収した場合はどうなるでしょうか。
この場合は「賃貸料相当額」と「徴収額」との差額が給与課税の対象になります。
「賃貸料相当額×50%」との差額ではありません。
固定資産税の課税標準額の改訂があった時
固定資産税の課税標準額は、3年に1度の評価替えによって見直されます。
直近の評価替えは令和6年度(2024年度)に行われたため、次は令和9年度(2027年度)、令和12年度(2030年度)…と続きます。
ただし、課税標準額が改訂されても、現在の20%以内の増減であれば賃貸料相当額を見直す必要はありません。
新しい賃貸料相当額を適用するタイミング
固定資産税の課税標準額が改訂された場合、新しい賃貸料相当額を適用するタイミングは、改訂後の第1期分の納期限の月の翌月分からとされています。
例えば、東京23区内の納期限は、第1期が6月、第2期が9月、第3期が12月、第4期が2月となっています。
したがって、6月の翌月である「7月」から改訂後の金額を適用することになります。
社宅における税務と社会保険の違い
ここまで、社宅における「税務上」の扱いを見てきました。
それでは、「社会保険」での扱いはどうでしょうか。
社会保険でも税務と同様に現物給与となり、標準報酬月額の算定に含める必要があります。
ただし、その金額は社会保険独自の「全国現物給与価額一覧表」に基づいて計算した額となります。
たとえば東京都の社宅の場合、一畳あたり2,830円で現物給与を計算します。
10畳の部屋であれば、2万8,300円です。
床面積が「平方メートル(㎡)」で表記されている場合は、1畳あたり1.65㎡に換算して計算します。
現物給与の額はこちらで確認できます。
日本年金機構|全国現物給与価額一覧表
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html
まとめると、社宅における税務と社会保険の違いは以下のとおりです。
| 無償で貸与している場合 | 家賃を徴収している場合 | |
| 税務 | 「賃貸料相当額(50%ではない)」が給与課税の対象になる | ・「賃貸料相当額×50%以上」を徴収している →給与課税なし ・「賃貸料相当額×50%未満」を徴収している →「賃貸料相当額(50%ではない)」と「徴収額」の差額が給与課税の対象になる |
| 社会保険 | 「現物給与の価額」(現物給与価額一覧表で計算)が標準報酬月額の算定対象になる | ・「現物給与の価額以上」を徴収している →標準報酬月額の算定に含めない ・「現物給与の価額未満」を徴収している →「現物給与の価額」と「徴収額」の差額が標準報酬月額の算定対象になる |
税と社会保険のどちらにおいても現物給与に該当させないようにするには、「賃貸料相当額×50%以上」と「現物給与の価額」のどちらか高いほうを家賃として徴収する必要があります。
社長(役員)の社宅で節税する方法
役員に会社から社宅を貸与し、その家賃を会社の経費することも可能です。
ただし、役員の社宅は従業員よりも注意して判断しなければならないポイントが多くあります。
そのため、独断で進めるのではなく、税理士に相談したうえで取り組むことをおすすめします。
以下では、従業員との違いを軸に、役員社宅を現物給与とせずに経費にする方法を解説します。
徴収額は「賃貸料相当額」
役員社宅の場合も、役員から一定の家賃を徴収していれば、税務・社会保険ともに現物給与の対象外となります。
社会保険については、従業員の場合と同じで「全国現物給与価額一覧表」から計算した額を役員本人から徴収すれば現物給与になりません。
一方、税務については異なります。
まず、現物給与としないための徴収額は「賃貸料相当額」となります。
「賃貸料相当額×50%以上」ではありません。
さらにこれは、役員の社宅が「小規模な住宅」にあたる場合です。
「小規模な住宅」に該当しない場合や「豪華な社宅」に該当する場合は、賃貸料相当額の計算方法が変わり、より厳しい条件となります。
以下、詳しく解説します。
小規模な住宅に該当する場合
「小規模な住宅」とは、以下の床面積条件を満たす社宅になります。
・建物の法定耐用年数が30年以下(主に木造住宅)
…床面積132㎡以下
・建物の法定耐用年数が30年超(主にRC・SRC造)
…床面積99㎡以下
(※)マンションなど区分所有の建物は「専用部分+共用部分を按分した床面積」で判定します。
この規模に該当する住宅であれば、従業員と同じ計算方法で計算した「賃貸料相当額」(50%ではない)を徴収すれば、現物給与になりません。
(前述の「賃貸料相当額の計算方法」を参照)
小規模な住宅に該当しない場合
「小規模な住宅」に該当しない場合は、「賃貸料相当額」の計算方法が変わります。
・自社所有の社宅
次の1と2の合計額の12分の1が「賃貸料相当額」になります。
1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(※)
(※)法定耐用年数が30年を超える建物は10%
2.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
・賃借している社宅
家賃の50%と、自社所有の方法で計算した額とのいずれか多い金額が「賃貸料相当額」になります。
豪華な社宅に該当する場合
床面積が240㎡を超える社宅や、プールなど個人の嗜好を著しく反映した設備がある住宅は、「豪華な社宅」と判断される可能性があります。
豪華な社宅の場合、これまでのような計算式は適用されず、相場どおりの賃料が「賃貸料相当額」となります。
役員社宅はとても魅力的な節税策ですが、従業員の社宅よりも注意点が多い制度です。
迷ったときは、新宿の税理士・中村太郎にご相談ください。
社宅と住宅手当の違い
最後に「社宅を完備することと、住宅手当を支給する方法では違うのか?」という疑問にお答えします。
住宅手当とは、基本給にプラスして金銭で支払われる給与の一つです。
どちらが金銭的に得になるかは一概にはいえないため、それぞれのメリットを踏まえて選ぶ必要があります。
年収からみた違い
住宅手当を支給するほうが従業員の年収は上がります。
年収を決め手に就職先を比較する人にとっては、住宅手当のほうがわかりやすい魅力となる可能性があります。
税や社会保険の手続きからみた違い
住宅手当であれば現物給与を心配する必要がありませんので、税や社会保険でのミスが起こりにくいといえます。
手取りからみた違い
社宅で現物給与にならない範囲の家賃を徴収すれば、税や社会保険の負担は変わりません。
一方、住宅手当であれば、手当で不足する分の家賃や手当にかかる税や社会保険を負担する必要があります。
住宅手当をどのくらい支給するか、社宅であれば家賃をどのくらい徴収するかは会社が決めるため、どちらが必ずしも得になるとはいえません。
しかし、一般的には社宅のほうが手元にお金を残しやすいと考えられます。
生活管理面からみた違い
社宅は住宅手当と異なり、「お金」で受け取るものではありません。
そのため、たとえば若い従業員の多い職場では、生活費の管理を助ける役割を果たすこともあります。
まとめ 社宅制度を上手に活用して節税をしよう
今回は、会社の社宅について、基本的な仕組みや種類、従業員社宅と役員社宅の違い、賃貸料相当額の計算方法、そして税務と社会保険の扱いの違いなどを解説しました。
社宅は、福利厚生の充実だけでなく、節税効果も期待できる制度です。
正しいルールを理解し、適切に運用することがポイントになります。

いかがでしたでしょうか。
今回は、社宅を経費にして節税する方法について解説しました。
家賃の徴収を誤ると「現物給与」とされ、税務や社会保険のミスにつながる恐れがあります。
特に、役員社宅の税務は従業員社宅よりも複雑で、独自のルールに注意が必要です。
当事務所では、社長様からのご相談に応じて社宅での節税対策もご支援しています。
福利厚生の充実と節税の両立を図り、会社をさらに成長させたい方は、ぜひ西新宿の税理士・中村太郎にお気軽にご相談ください。
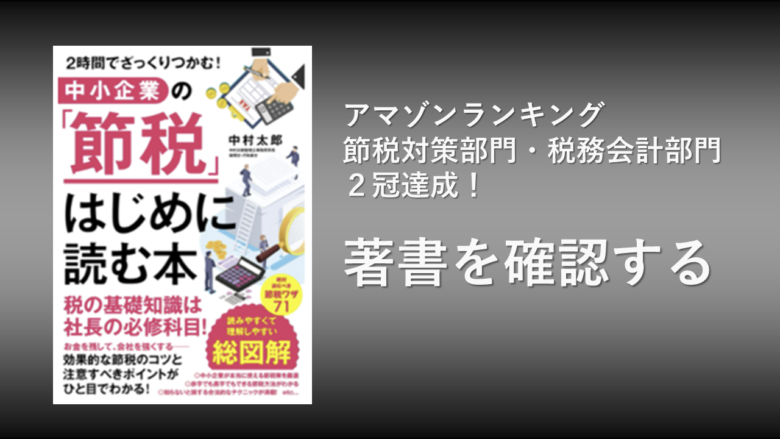















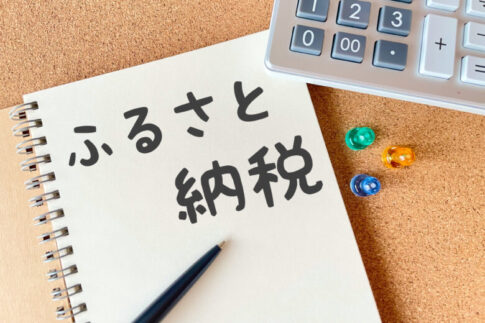



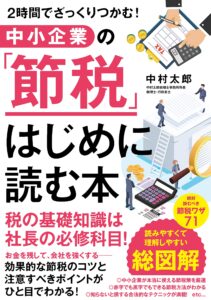

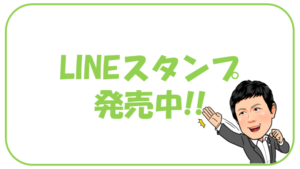
まいど!西新宿の税理士 中村です!
福利厚生の充実は優秀な人材の採用や定着につながり、その費用はもちろん会社の経費になります。
社宅の導入もその一つです。
しかも従業員だけでなく、役員の社宅でも経費になりますから、社長の住まいを会社の経費にすることも可能です。
ただし、これらを無対策で行うと、役員や従業員の「現物給与」として扱われ、税や社会保険の徴収ミスにつながることがあります。
さらに役員の場合は、従業員よりも厳しい条件を満たさなければ、経費にならないリスクもあります。
本記事では、そうしたミスを防ぎ、正しく社宅を経費にする方法を解説します。